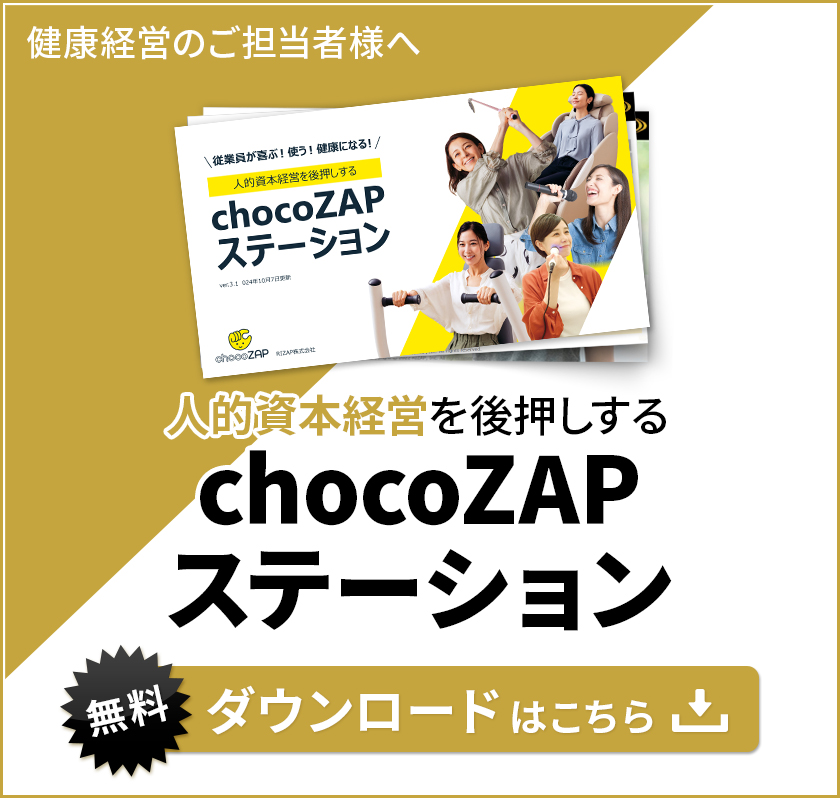健康経営のための福利厚生とは?
健康経営への取り組みをしている場合には、福利厚生の導入・見直しをおすすめします。
健康経営は単年だけで結果が出る取り組みではなく、健康や運動について高い意識を持つ文化を社内で醸成できるかどうかが重要なポイントとなります。
特に健康経営優良法人の取得を考えている場合には、「従業員の心と身体の健康づくりに関する具体的対策」の項目で食生活改善や運動機会の増進に向けた具体的な支援を行っているかが問われています。
環境整備や金銭的な支援だけではなく、従業員が自発的に利用したくなる魅力的な福利厚生が有効でしょう。
関連記事:働き方改革のカギは健康経営|取り組みメリットと生産性向上のポイント|RIZAP 健康経営コラム
サービス資料「chocoZAPステーション 」をご覧いただけます
人手不足等のさまざまな人事課題を解決するため、福利厚生を充実させたい、従業員に人気のある福利厚生を取り入れたいというご要望はございませんか?
従業員に人気のある健康分野の福利厚生として、サービス資料「chocoZAPステーション」をお届けします。
chocoZAPをはじめとしたRIZAPブランドにお得に通えるchocoZAPステーションの概要資料です。従業員の健康増進や運動不足対策に、多くの企業で福利厚生として選ばれています。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
資料をダウンロードする
【種類別】健康経営につながる福利厚生12選
ここでは健康経営推進に役立つ福利厚生を紹介します。自社に取り入れられそうな福利厚生の制度や取り組みがあるかどうか、検討してみてください。
運動不足解消サポート
運動促進を福利厚生を含めて企業規模で取り組むことで、健康増進以外にもチームビルディングやコミュニケーションの促進、ストレスの解消にもつながります。そして、心身共に健康的な従業員が増えれば業務への集中力が増し、病欠者も減るので生産力アップも期待できます。
1. スポーツジムの利用補助
昨今はテレワーク推進の影響もあり、通勤が減ったことにより、運動不足になりがちといった人も多く見られます。
運動不足の解消のためにジムに通う従業員は積極的な一部の社員にとどまることが多いですが、福利厚生としてスポーツジムにお得に通える環境整備を行うことで、一人でも多くの従業員がスポーツジムに通うことを後押しすることにつながります。
昨今、プールや筋肉トレーニング器具、スタジオなどを兼ね備えた一般的な大型ジムだけでなく、コンパクトな面積で24時間気軽に通えるジムも増えています。会社の近くや家の近くにコンビニ感覚で通える手軽さから急速に会員数が伸びており、福利厚生として導入する企業も増えています。
従業員が喜ぶジム法人会員の福利厚生
従業員の健康を後押しするだけでなく、従業員自身が喜ぶ健康増進の福利厚生なら話題のchocoZAPの利用できるchocoZAPステーションがおすすめです。chocoZAPステーションの概要・メリット・対象ブランド・価格・特典等をご案内しています。
資料ダウンロードはこちら(無料)
2. オフィスにジム設置
福利厚生として、オフィスの一角にワークアウト効果の高いマシンを設置するなどジムスペースを設け、職場環境でいつでも健康増進ができる取り組みです。運動できる環境の構築により、従業員が仕事の空き時間や休日などちょっとした時間にジムを利用できるため、従業員の健康増進が期待できます。
運動するだけでなく、ストレッチを行えるスペースを設けたり、ヨガを実施するなど幅広い取組みを行うことで多くの従業員の興味関心を得ることが期待できます。
食事補助の導入
食事に関する補助は、食費の軽減や健康維持などにもつながるため、求職者からも従業員からも好まれやすい福利厚生です。
食事補助を通して豊かな食生活を送れるようサポートすることにより、従業員の健康増進だけでなく、従業員満足度の向上およびモチベーションアップが期待できます。
3. 食事代の補助
従業員の日々の食事代を軽減するために行うのが食事補助です。食事は従業員が毎日することなので、その食事代の補助があることで金銭的に助かる場面が多くなるだけでなく、金銭的な負担が少なく健康に配慮した食事を選びやすくなるなど健康面へのメリットが考えられます。
地域が幅広くコンビニや飲食店で幅広く使える補助であれば、一人暮らしでなかなか調理が難しい従業員でもおにぎりやパンだけでなくおかずや野菜のメニューなどをプラスすることで毎日の食事のバランスが整いやすくなるでしょう。
4. 社食サービスや置き型社食の導入
場所やコストはかかりますが、社員の食生活に直結する有効な福利厚生が「社食サービスの導入」です。昼食は社食で食べる従業員も多いので、一日に一度でも野菜を豊富に使った栄養バランスのよい食事を提供することは、従業員の健康維持に有益です。
コストやスペースの問題で社食の導入が難しい企業には、お弁当や給食の「配達サービス」や、冷蔵庫にあるメニューをいつでもレンジで解凍して食べられる「設置型サービス」という選択肢もあります。企業の規模やニーズに応じて選ぶのがおすすめです。
予防サービスの導入
病気や慢性的な体調不良に至らないよう、また従業員が元気に仕事に取り組んでもらうためには企業の施策として健康管理を推進していく必要があります。
健康リスクが低い従業員の労働生産性損失コストが年間推計56.4万円であるのに対して、健康リスクが中の従業員では1.2倍(年間推計66.8万円)、健康リスクが高い従業員は2.8倍(年間推計159.4万円)と非常に差があることも示されており、健康リスクの予防に対して注目が集まっています。
参照元:日本労働研究雑誌 2018年6月号(No.695)掲載 古井祐司(東京大学特任教授)村松賢治(東京大学受託研究員)、井出博生(東京大学特任准教授)「中小企業における労働生産性の損失とその影響要因」
5. 健康診断や人間ドックなどの医療費補助
従業員に対して定期的に健康診断を受診させることは法定福利厚生に含まれており、企業の義務です。そして、法定福利厚生である健康診断に加えて人間ドッグ受診費用の一部を補助する福利厚生を取り入れれば、従業員のさらなる健康維持・増進につながり、欠勤や病欠による生産力低下を防げます。
定期的な健康診断は従業員一人一人の健康意識の向上にもつながり、社内外での生活が整いやすくなるというメリットも挙げられます。また、従業員が安心して働ける環境を整えることで従業員の会社への帰属意識の高まりや、社外からのイメージアップへとつながることも期待できます。
6. ウェアラブル端末の配布
従業員の健康増進や運動不足の自覚を促す一つのきっかけとして、ウェアラブル端末を従業員に配布・貸与する企業が増えています。
ウェアラブル端末は、一日の運動量や睡眠の質などを計測する機能があるものも多く、中には休憩や運動を促し長時間の座りすぎを解消を促してくれるものもあります。
今まで漠然と運動不足を感じている場合、数値やグラフなどで運動量の少なさを自覚することで運動不足解消のキッカケになる可能性も高いでしょう。少しでも従業員自身に自分の体に興味を持ってもらうきっかけとして注目を集めています。
メンタルヘルス対策
福利厚生の整備は、新規人材の獲得や従業員満足度向上のために行うイメージがありますが、内容を精査することでメンタルヘルスケアにも応用可能です。
メンタル不調になることで仕事に集中できなくなる可能性が高く、対策が必要です。病欠や休職による生産性の低下を防げますし、従業員自身が積極的にメンタルヘルスに取り組むようになるという効果も期待できます。
7. 相談窓口の設置
健康やメンタルヘルスに関する相談ができるカウンセリング室などの窓口を設置する福利厚生も、多くの企業で取り入れられています。従業員が抱える心身の悩みを産業医や専門家に相談し適切なアドバイスや支援を受けることで、ストレスやうつ病などの予防につながります。
カウンセリング室や窓口を設置することで、従業員は健康に関する問題を解決して仕事に集中できるようになるため、モチベーションが向上して生産性の向上につながることが期待できます。
関連記事:EAPとは?導入されている理由、効果、気を付けるポイント
8. ストレスチェックの実施
ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックを実施することは、メンタルヘルス不調となることを未然に防止する一次予防につながります。従業員が自分の現在の精神状態を見直し、メンタルヘルスの不調の発見や改善にいち早く取り組めるようにする目的があります。
厚生労働省の公表によれば、常時50人以上の従業員がいる事業所において毎年1回、ストレスチェックを全ての従業員に対して実施することが義務付けられていますが、50人未満の事業所に関してもメンタルヘルス予防として実施することでメンタルヘルス不調の未然予防として効果が期待されます。
ストレスチェックは健康診断と同様、福利厚生費として損金に計上することが可能です。福利厚生費として計上するためには、すべての従業員が対象かつ社会通念上、常識と考えられる範囲の金額という2つの要件を満たしている必要があります。
関連記事:ストレスチェック制度とは?対象者、目的、メリット、実施方法
治療と仕事の両立支援
長期にわたる治療等が必要な疾病のため、一定期間の休職などを経て、通院による治療を受けながら仕事をしている労働者が増加しています。治療などを理由に退職を迫られている従業員がいても、企業が仕事との両立を支援できれば退職せずに働き続けられる可能性があります。
これまで企業の戦力として貢献してくれた従業員の力を今後も借り、健康増進と仕事の両立を目指す複利厚生は必要不可欠でしょう。両立支援によって従業員が安心して働き続けられる環境を整備することで、生産性の向上につながります。
9. 傷病休暇・病気休暇制度の整備
長期にわたる治療等が必要な疾病等、治療を受けながら仕事をする従業員をサポートするために付与される休暇です。治療・通院のために時間単位や半日単位で取得できる休暇制度や、年次有給休暇とは別に使うことができる病気休暇のほか、療養中・療養後の負担を軽減する短時間勤務制度等も考えられます。
病気休暇制度とは私傷病の療養のために、年次有給休暇以外で利用できる休暇制度です。取得できる要件や期間は、労使の協議あるいは休暇を与える使用者が決定することが一般的です。治療や療養等に備えた年次有給休暇の取り控えが減少することが期待できます。
また、風邪や感染症などの突発的な体調不良時に取得できる病気のための休暇を有給休暇と別に設けておくことは万一に備えたセーフティーネットとなり、労働者の安心につながります。
10. フレックスタイム・テレワーク制度の導入
勤務時間や勤務場所に関する自由度が高く、多様な働き方ができる職場を実現できれば、治療中の従業員だけでなく多くの従業員に働く機会を与えられます。ワークライフバランスの実現が重要視されている現在では、従業員へ快適な働き方を提供する福利厚生も増加しています。
フレックスタイムやテレワーク制度を導入することで、治療中のため出社やフルタイム勤務が困難な従業員に、キャリアを途絶えさせずに働いてもらうことが可能になります。優秀な人材の離職を回避できるだけでなく、多様な働き方を可能にする福利厚生は従業員のモチベーションアップにつながり、離職率の低下や生産性向上が期待できます。
働き方の整備
健康増進にはワークライフバランスの実現が欠かせません。従業員へ快適な働き方は従業員の健康増進に直結します。
ワークライフバランスが成り立たないような働き方をしていると、従業員は自らの健康を顧みる暇がなくなるだけでなく、長時間労働や優先度として仕事が大きくなりすぎることで健康状態がおろそかになり、身体だけでなく精神的にも不調をきたしやすくなります。
多様な働き方を可能にする福利厚生は従業員の健康増進だけでなく、モチベーションアップにもつながり、離職率の低下や生産性向上が期待できます。
11. 短時間勤務やフレックスタイム制度など業務時間に関する整備
働く時間に関する制度は、従業員の働きやすさだけでなく健康増進にもかかわる重要な制度です。勤務地や結婚や子ども・介護の有無などによって勤務時間の縛りがどの程度きつく感じるのかは人それぞれですが、従業員の状況に応じて勤務時間を調整できることは勤務を継続できるか、離職しなければならないかの選択に直結することも多いだけでなく、少しの無理を継続することで心身の負担になっていることも少なくありません。
やりくりすれば何とか大丈夫かもしれないというようなぎりぎりの働き方は、急な残業や忙しさなどに対応し続けることは難しく、無理を重ねて休職や離職をせざるを得ない状況に追い込まれやすくなります。
従業員の労働時間の時間調整が可能になる福利厚生を導入することで健康的に働き続けられる企業を目指すことは、従業員に常に求められているでしょう。
12. テレワーク制度など業務場所に関する整備
テレワークには働き方や健康増進にとって、メリット・デメリットが両方ある制度です。満員電車や渋滞に巻き込まれることなく仕事が可能であったり、業務終了とともに業務以外の必要事項に通勤時間をカットして取り掛かれる、自宅に仕事環境が整っていればストレスを軽減しながら仕事ができるなど多くのメリットがあります。
一方デメリットとしては、通勤が重要な運動習慣の一部であったことがわかり知らず知らずのうちにできていた最低限の運動もなくなってしまうこと、職場で仕事をしないことから業務量の把握が難しくなり長時間残業につながりがちになることなどが考えられます。
しかし、治療との両立や妊娠中の勤務、家族の看病など通常の勤務では働き方においても健康管理上でも仕事が難しいケースにおいてテレワーク制度が従業員を助けてくれるケースは多々あります。
従業員の細やかなニーズを吸い上げ、勤務地に関して柔軟な対応が可能となる福利厚生を導入することで従業員が健康的に働き続けられる環境を作り出すことにつながります。
健康経営を実現する福利厚生を選ぶポイント
健康経営を実現する福利厚生を選ぶ際には、押さえておきたいポイントがあります。自社の従業員や企業にとって満足度の高いサービス・制度となるよう、以下で述べる点には注意しましょう。
福利厚生の目的を明確にする
福利厚生の目的を明確にすると、必要な予算内で満足できるサービスを導入できます。
目的をはっきりと示さずにピックアップすると、必要でないものを選んでしまったり、後々プランを追加しなければならなくなったりと、手間も費用も余計にかかってしまう恐れがあります。
例えば、採用強化や従業員満足度の向上、生産性の向上など「何のために導入するのか」という点をはっきりさせましょう。
従業員のニーズを確認する
従業員のニーズを把握するためには、導入前にはアンケートやヒアリングを実施し、意見を収集します。
福利厚生にはさまざまなプランやサービスがあり、他社の導入事例を見ていると、良さそうなものが数多く見つかるでしょう。しかし、前述の通り、従業員のニーズは企業によってそれぞれです。そのため、他企業で喜ばれたものが必ずしも自社で歓迎されるとは限りません。
実際に働く従業員の声を聞くことで、「自社に必要なものは何か」を見極めることができます。
目的とニーズを達成するためのサービスを導入する
目的とニーズを明確にし、それらを達成できるサービスは何かを検討しましょう。
サービス内容や運用方法、料金体系などはさまざまです。自社に合ったサービスを選ぶには「目的を達成し、従業員のニーズを満たすものはどれか」という視点で選定することが大切です。
定期的な見直しをする
サービス導入後も、従業員のライフスタイルや価値観は移り変わります。そのため、定期的に今のニーズにマッチしているかをチェックし、必要に応じてプランを見直しましょう。
特に注意すべきは、サービスの利用率です。数値が高いことは、満足のいくサービスが提供できていることを意味するため、問題ないでしょう。しかし、低い場合は再度ヒアリングを行うなどしてニーズをブラッシュアップすることが重要です。
より良い制度にするための改善策を講じ続けることで、従業員の満足度の向上を図れます。
健康増進につながった事例
福利厚生で健康を促す事例として下記のものが参考になります。
健康への気づきを促し運動習慣化を後押し|社会保険労務士法人 ベスト・パートナーズ
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ様は、体重や体脂肪が気になるスタッフの健康を考えたときに初心者の運動実践や、健康習慣をサポートできるような制度や仕組みに興味を持たれ、chocoZAP(RIZAP)の法人会員※1を導入されました。
従業員の皆様からは、必ずRIZAPやchocoZAPの店舗へ行かなければならないのか?などの懸念する声やジム通い初心者の中にはトレーニングマシンを使うどころか店舗に行くことにも抵抗がある様子が見られましたが、導入後は下記のようなお声が寄せられました。
- 週末の買い出しのついでにchocoZAPに寄れるので週1で通えるようになった
- 気軽に利用できるので、筋トレをするきっかけになった
- chocoZAPが会社の近くにあり、5分くらいの運動なら続けられたので、習慣化できた
- chocoZAPに週1回程度通うようになった
- 体組成計とヘルスウォッチをいただき、健康ポイントも付くので、体重や血圧を毎日測る習慣がついた
- もともと週1回の運動はしていたけど、週2~3回程度行うようになった。また、筋トレを行うことにより姿勢に気を付けるなどを意識するようになった
- 筋トレをする習慣が身についた
導入前にあった従業員の方々の不安や懸念に対してRIZAPとベストパートナーズ様がどのような対応を行ってきたのか、どのような対策を行った結果習慣化につなげることができたのかを下記の資料で詳しくご覧いただけます。
※1 本事例でご紹介している「ゴールドプラン」はchocoZAPステーションの前身サービスです。
社会保険労務士法人ベスト・パートナーズ様の詳しい事例はこちら
ウォーキングポイントをレジャーや薬代に|株式会社富士通ゼネラル
もともと健康増進のためにウォーキングイベントを自社で開催していましたが、さらなる活性化を目指して福利厚生制度を活用しました。具体的にはウォーキングすることでポイントが貯まり、そのポイントをレジャーや常備薬の購入費用に充てられる制度があります。制度が浸透してウォーキングイベントの参加者も増え、当初の目標参加人数を達成しています。
参照元:株式会社富士通ゼネラル
健康状況予測システムで健康促進|ナガオ株式会社
従業員の健康増進や健康寿命の伸長を目的に、将来的な健康状況を予測するシステムを導入しています。特に、食生活の改善に力を入れているのが特徴です。肥満傾向などが明らかになった従業員がいれば、アドバイスを行い将来的な不調を未然に防ぐ努力をしています。また、ランニングやスポーツ大会への参加なども積極的に行い、従業員の健康促進に一役買っています。
参照元:健康経営優良法人取り組み事例集|経済産業省
まとめ
福利厚生は従業員が働きやすい職場環境づくりに効果的な制度です。導入時には従業員からどのような福利厚生が必要かをヒアリングして、適切な福利厚生を提供してください。また、導入後も定期的に福利厚生の効果を見直しアップデートしていくことで、さらに企業経営への好影響が期待できます。
サービス資料「chocoZAPステーション 」を無料で公開
福利厚生を検討する際に、「従業員に積極的に利用してもらえるサービス」や「従業員の健康増進に貢献するサービス」についてお悩みのご担当者様も多いのではないでしょうか?
そこで、従業員に人気のある健康分野の福利厚生として、サービス資料「chocoZAPステーション」をお届けします。
chocoZAPをはじめとしたRIZAPブランドにお得に通えるchocoZAPステーションの概要資料です。法人会員を活用することで福利厚生の利用率を高めることに活用することもでき、利用率が向上すれば従業員の健康増進にも役立てることができます。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
資料をダウンロードする
![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)