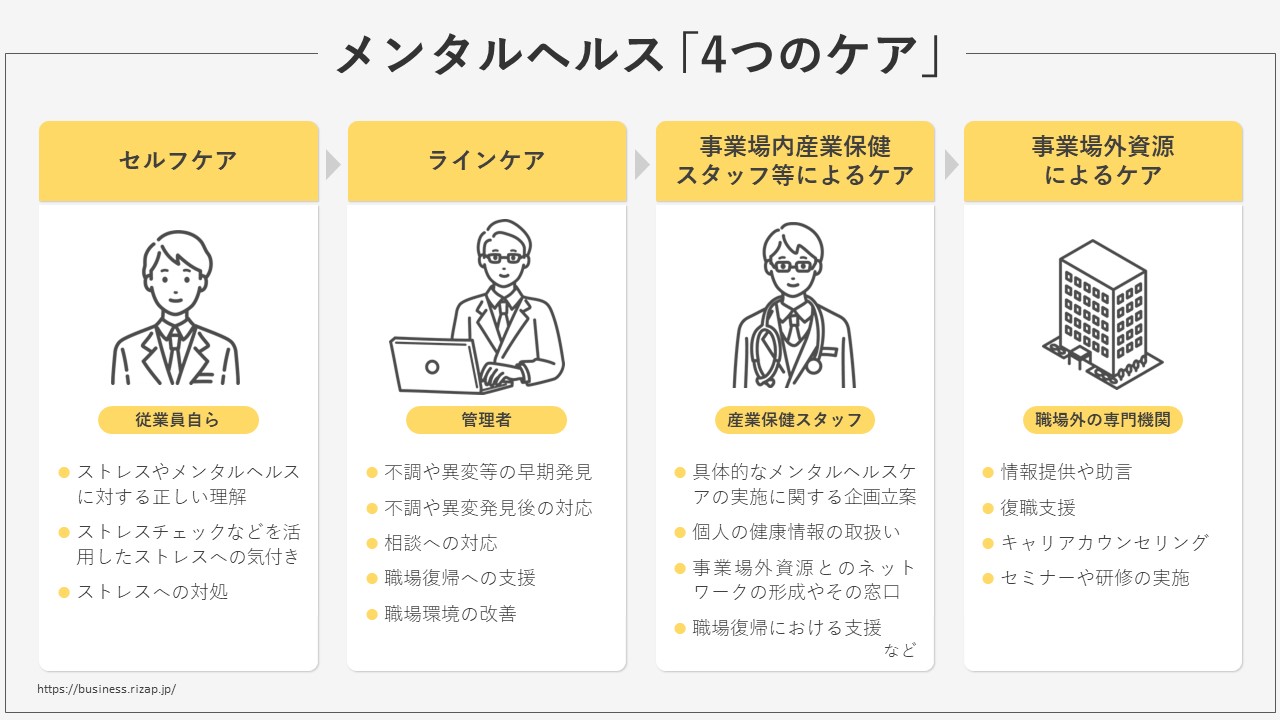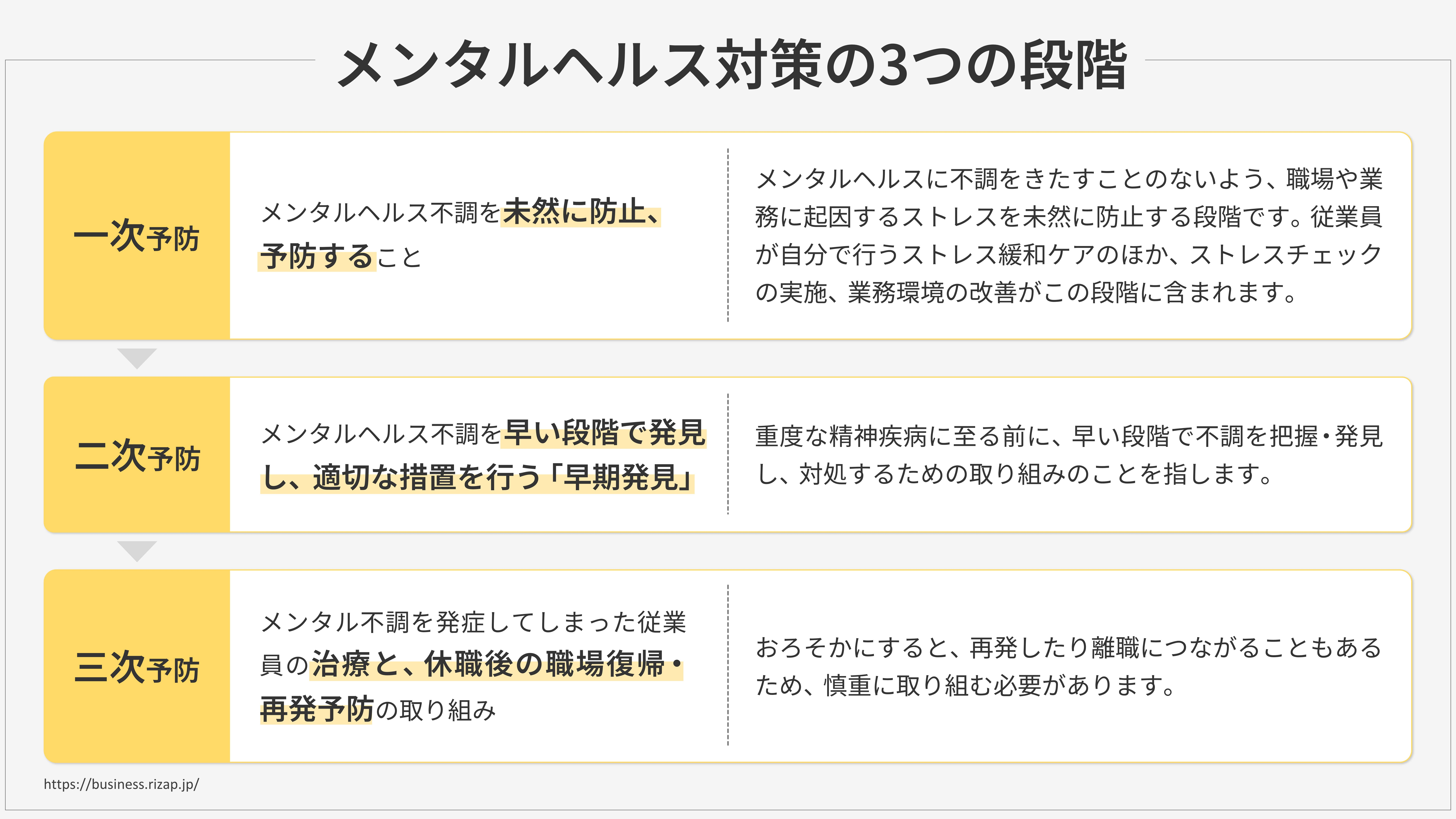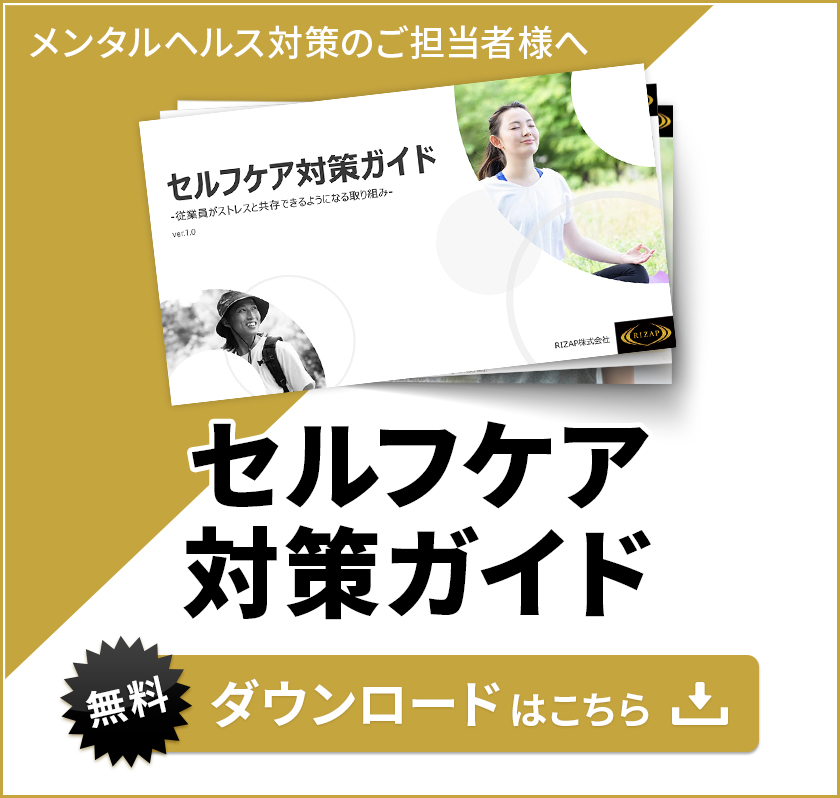セルフケアとは
「セルフケア」は従業員が自分自身で行うメンタルヘルス対策で、従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することを指します。簡単そうですが実は正しい知識がないと適切に対処できません。
例えば、体や気持ちに異変が生じていても「今の自分は、うつ病かもしれない」と、自発的に気付いて対応できる従業員ばかりではありません。また異変の度合いや、生じる症状や頻度は、人によってそれぞれであるため、判断が難しい場合があります。
ストレスの認知や、その反応に自ら気付くためには、従業員一人ひとりがストレス要因に対する反応や、心の健康について理解するとともに、気付こうとする姿勢が必要です。自ら気付き、対応する「セルフケア」を適切にできるようになるには、教育研修の機会を設けて、意識を高めていくことが重要です。
このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。
4つのケアの一つ
このセルフケアは、厚生労働省がメンタル不調と向き合うための有効策として発表した「4つのケア」の一つです。セルフケアのほか、「ラインケア」「事業場内産業保健スタッフ等によるケア」「事業場外資源によるケア」が推奨されています。
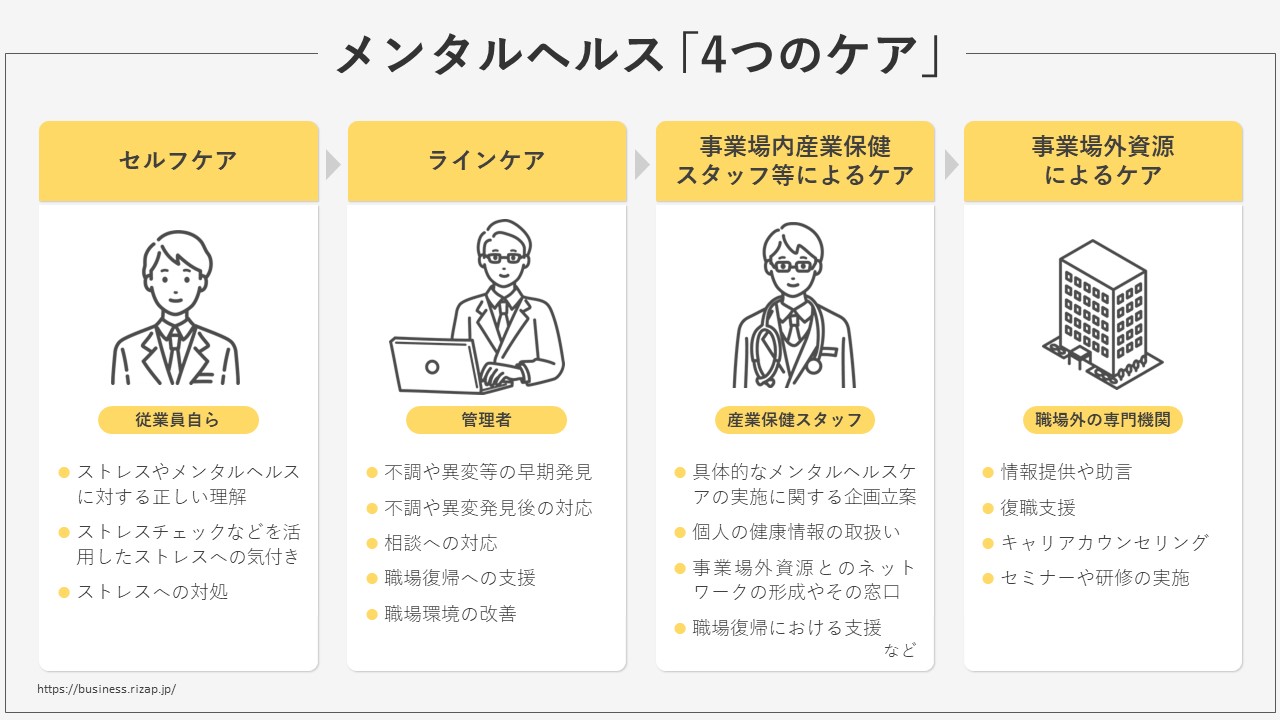
関連記事:メンタルヘルス対策の具体例|対策の基本と有効な取り組み
お役立ち資料「セルフケア 対策ガイド」をご覧いただけます
メンタルヘルスケアの一つとしてセルフケアを検討する際に、どのように進めたらよいか、また施策や効果について知りたい方も多いのではないでしょうか?
そこで、セルフケアの施策を実施しようとお考えのご担当者様に向けて「セルフケア対策ガイド」をお届けします。
セルフケアに関する情報を体系的におさえ、組織としてセルフケアを高めていくために本資料を作成しました。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
資料をダウンロードする
セルフケアのポイント:ストレスサインとストレス要因に気づくこと
ストレスを過度にためず、適度なストレスとうまくつきあっていくコツのひとつは、「自分のストレスに気づく」ことです。ここでは、ストレスへの気づきのポイントについてご紹介します。
ストレスサインへの気づき
まず1つ目は、こころの不調としてのストレスサインへの気づきです。「なかなか眠れないなぁ」、「最近なぜかイライラしているなぁ」などの変化は、こころの不調としてのストレスサインのひとつです。このようなサインを放っておくと、ストレス性の疾患など治療が必要なレベルに移行する可能性があります。サインに気づいたときは、早めに相談する、対処するなどの対応をとることが大切です。
こころの不調としてのストレスサインの主なものは以下のとおりです。以下のような症状が2週間以上続く場合は「うつ」が疑われますので、専門家(精神科、心療内科)に早めに相談することをおすすめします。
- こころの面:悲しみ、憂うつ感、不安感、イライラ感、緊張感、無力感、やる気が出ない
- 体の面:食欲がなくなる、やせてきた、寝つきが悪い、朝早く目が覚める、動悸がする、血圧が上がる、手や足の裏に汗をかく
- 行動の面:消極的になる、周囲との交流をさけるようになる、飲酒、喫煙量がふえる、身だしなみがだらしなくなる、落ち着きがない
引用:厚生労働省「働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト こころの耳」
ストレスの原因となりうる要因
セルフケアの必要性とメンタルヘルスについて対策を考える際、ストレス要因を理解することが重要です。
ストレス要因となるようなきっかけや出来事が複数重なった場合や、長く続いた場合など、こころの不調につながることがあります。ストレスの原因となりうる要因として、自分がどのような出来事を体験しているのかに気づくことは、とても大切なことです。
医学や心理学の領域では、心身にかかる外部からの刺激を「ストレッサー」と言い、働くなかでのストレッサーには3種類あります。
- 物理的ストレッサー:騒音や温度・湿度による不快、眩しい暗いなどの環境刺激
- 化学的ストレッサー:たばこや空気汚染、ほこりなど化学物質による刺激
- 心理・社会的ストレッサー:人間関係、経済トラブル、課題に対する負担など
出典:厚生労働省「働く人のメンタルヘルスポータルサイト「こころの耳」「1 ストレスとは」」
上記の心理・社会的ストレッサーについて、ストレスの原因になりやすい出来事の例として以下のようなことが考えられます。
《生活上の出来事》
- 自分や家族の誰かが病気・怪我・災害などの被災体験をした
- 子どもの進学、夫婦や親子の不和など、家庭内の人間関係に問題があった
- ローンや借金、収入の減少などの金銭問題があった
- 引越しや騒音などの住環境の変化があった
《職場での出来事》
- 仕事での失敗やミスがあり、責任を問われた
- 仕事の量や質、勤務時間などが変化した
- 上司や同僚、部下などと人間関係でのトラブルがあった
- 昇進や配置転換、転勤など役割、身分の変化があった
このような出来事があった場合には、ストレスの原因として体調の変化につながる場合もあることを理解し、自分自身や同僚、スタッフ間などでお互いを気にして体調に配慮しあうなどすることで変化に気づきやすくなります。
体調で気になる点がある場合には、家族や、職場の上司や同僚、産業保健スタッフなど、相談しやすい人に相談してみるのもよいでしょう。
セルフケアを推進する重要性
厚生労働省は、地域医療の基本方針となる医療計画に盛り込むべき疾病として、従来より「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」「糖尿病」の4つの疾病を位置付けていましたが、2011年から「精神疾患」も加わり、これら5つの疾病対策に注力しています。
参照:第10回第8次医療計画等に関する検討会「5疾病・5事業について(その1;5疾病について)」
厚生労働省が毎年実施している「労働安全衛生調査(実態調査)」によると、仕事の質や量に対する不安やストレスを抱える労働者の割合は、2012年から2018年にかけておおむね約60%近くで推移しています。
実際、仕事のストレスのため「うつ病」などの精神障害を発症し、労災と認定された件数は2021年に過去最多となりました。※1
このような中で、心の健康問題が従業員、その家族、事業場及び社会に与える影響はますます大きくなっており、事業場においてより積極的に従業員の心の健康の保持増進を図ることは非常に重要な課題となっています。
今やメンタルヘルスは日本が抱える社会的課題となってきています。
参考:厚生労働省「令和2年度「過労死等の労災補償状況」を公表します」
また、「精神障害に関する事案の労災補償状況」の調査においても、精神障害による労災を申請する件数が年々増加傾向にあることが明らかになっています。従業員が心身に不調をきたすと、従業員の生産性が落ちたり、更には休職・退職につながりかねません。健全な企業活動を維持するには、従業員がセルフケアを実施することが重要なのです。
従業員のメンタルヘルスを考える中で最も重要なのがセルフケアです。自らがストレスを認知し、適切に対処できれば、不調を防ぐことができるためです。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。
セルフケアを実施する企業のメリット
従業員のセルフケアを推進する企業が増えているのは、企業を支える従業員が活力を持って健康的かつ長期的に働き続けることを可能にするための施策として「メンタルヘルス対策に投資」する必要があるからです。
この投資によって企業が得られるメリットとしては、主に以下の点が挙げられます。
- アブセンティーイズム・プレゼンティーイズムの解消
- 離職率の改善
- 従業員の活力向上
- 職場の活性化
- 労働災害の予防
- 業務ミスや企業イメージ悪化のリスク減少
- 医療費の削減
- 労働生産性の向上
- 社会評価と企業イメージ向上
関連記事:メンタルヘルスとは?職場のメンタル不調の予防と対策
セルフケアを身につける従業員のメリット
セルフケアを身につけることで、自分自身のストレスの状況や心身の変化や不調に自らが気づくことができます。これは、健康管理を行う上で非常に大切なことで、気づくことが対処することにつながり、病気の進行や不調の改善に大きく役立ちます。健康の一次予防(未然予防)として、もっとも身につけたい技術となるでしょう。
セルフケアを日ごろから実践することで大きな体調不良につながりにくくなるため健康リスクを低下させるだけでなく、仕事の生産性向上や職場での人間関係、コミュニケーション活性化にもつながり、QOL向上となるでしょう。
職場内で行えるセルフケア実践例
個人でできるセルフケアは、基本的には従業員自身が行うものです。そのため企業は、様々な角度・方法で従業員に対してセルフケアの重要性を伝える必要があります。
セルフケアの理解を促す
セルフケアスキルを高めるには、一人ひとりに気づきを与える教育研修を定期的に開催することが重要です。
従業員にセルフケアの重要性を伝えるため、セルフケアセミナーや研修を行ったり、定期的に情報発信をしていくことが大切です。定期的に開催・発信することで、それぞれが具体的に何をすれば良いかを理解し、業務への効果が表れやすくなります。
何より、自分自身をケアすることの重要性は日頃から忘れがちなため、動機づけの機会として有効になります。
食習慣の改善を促す
食事をしっかり取ることも大切なことです。忙しいからといってランチを抜いたり、食事を適当に取ったりしていると、身体の不調を招いてしまいます。できるだけ栄養のバランスを考え、好き嫌いせずに楽しみながら食事する大切さを伝えることで、心も身体も満たされるでしょう。
また、食事はコミュニケーションの機会にもなります。誰かと食事をとることでメンタルヘルスにも好影響が期待できます。
方法としてはセミナーや研修など定期的に開催する方法や、福利厚生でバランスの整った食事を昼食に選びやすくする食事補助の提供や、社員食堂がある場合には食堂にポスター等の情報発信をすることも有効です。
運動の習慣化を促す
長時間にわたって座ったままや同じ姿勢を取りつづけていると、血流が悪くなり、身体に悪影響を及ぼす原因になります。定期的に立ち上がって歩いたり、ストレッチをしたりして適度に身体を動かすことで、凝り固まった身体をほぐし、気分転換にもなります。
企業の取り組みとして、運動の大切さ・習慣化への呼びかけとして定期的にセミナーを開催したり、朝や昼食後に5分間程度全員で行うストレッチや筋トレを取り入れるなども有効です。テレワークの場合座る時間がより増加することから、週に1度オンラインレッスンとして時間をとり定期的に体を動かす機会をつくるのもよいでしょう。
また、福利厚生でスポーツジム利用の補助や会社に体を動かすコーナーを作ったり、従業員が体を動かすイベントを定期的に設けるなど、運動習慣化を会社全体で促していることが従業員に伝わるように働きかけていくことが大切です。
睡眠の重要性を伝える
睡眠の間に脳や身体がリセットされ、翌日への英気が養われます。そのため、睡眠の質はメンタルヘルスにとっても非常に重要です。睡眠負債という言葉をよく最近耳にします。睡眠負債とは睡眠の借金であり、毎日少しずつ積み重なる睡眠不足のことです。
十分な睡眠がとれていない場合、脳のパフォーマンスは日に日に落ちて仕事の生産性も低下します。1日6時間の睡眠を2週間続けた場合、2日徹夜した後と同程度に脳のパフォーマンスが落ちるといった研究結果もあります。
睡眠の重要性や快適な睡眠を従業員がとれるよう、睡眠に関するセミナーや情報提供を定期定期にしていくことが大切です。最近ではウェアラブル端末や、睡眠の質を計測できるアプリ等もあるため、そのような器具・機器の補助や提供などでも従業員の睡眠の質にたいしてアプローチすることも可能です。
肩こり・腰痛対策を実践する
プレゼンティーイズム(presenteeism)とは、欠勤には至っていないものの「健康問題が理由で生産性が低下している状態」を指します。言い換えると、心身の不調によって、パフォーマンスが思うように出せない状況のことです。
参考:経済産業省「健康経営オフィスレポート」p.7
そのプレゼンティーイズムの原因の一つとして、運動器・感覚器障害(腰痛・肩こり、頭痛、眼精疲労)があげられます。心身の状態を活性化するために運動は必要ですが、肩こりや腰痛を直らないものとして慢性化させてしまうことでプレゼンティーイズムの原因になるため、放置せずに対策することが必要です。
特にテレワークの普及に伴い、環境が変化したことで腰痛になる人が増えています。腰痛・肩こりの主な原因としては床や椅子への座り方や生活習慣によるものが大きいといわれています。
これらの要因を解消するために肩こり・腰痛対策となるセミナー・研修の実施や、予防するための運動習慣の後押しとして福利厚生の見直し、運動のキッカケづくりとしてのイベントの開催なども有効です。
関連記事:【RIZAP監修】テレワーク中の腰痛対策とは ❘ 生産性を上げる
ヘルスリテラシーを高める
セルフケアや健康や疾病について、行動に移すかどうか本人が判断するためには「ヘルスリテラシー」の力が重要です。ヘルスリテラシーを高め、情報の入手から活用までの一連の行動は健康を守るために非常に重要でありながら、その能力を身に着けるにはそれなりの技量が必要です。
関連記事:健康リテラシー向上のための取り組みとは?ポイント・事例
ヘルスリテラシーを高めるには、健康に関する情報を定期的・長期的に設けるだけでなくテーマや角度を変えて実施した内容を評価し、改善し続けることが大切です。
また従業員への直接的なアプローチだけでなく、集団で取り組む環境を整えたり部署単位でまとまって取り組むような仕組みにすることで、健康に無関心だとしても「みんながやってるから自分もやらないと」と思い行動する人も増えてくると想定されます。環境からのアプローチも検討していきましょう。
コミュニケーションを活性化する
親しい人と話すことで気持ちが自然に落ち着くものです。一人で抱えていた悩みを共有することで、新たな解決策のヒントが見えてくるかもしれません。また、笑うこともストレス発散方法として有効です。もし気分が少し落ち込んだり、体調が思わしくないと感じたりした場合は、適度なコミュニケーションを取ってみるのがよいでしょう。
コミュニケーションを活性化するには、まずは自社の社内コミュニケーションの活性化度や課題を確認し、どのような施策が必要かを検討することが大切です。そのうえで、リフレッシュスペースやミーティングスペースの確保等で交流を促進する環境を整えたり、業務時間以外で社内イベントや社内サークル・部活など、従業員の興味関心をもとにコミュニケーションの場を作るのも有効な方法です。
関連記事:社内コミュニケーションを活性化するアイデアと成功事例
ストレスチェックを実施する
ストレスチェックは、一次予防である「メンタルヘルス不調となることを未然に防止する」ことを目的としています。つまり、従業員が自分の現在の精神状態を見直し、メンタルヘルスの不調の発見や改善にいち早く取り組めるようにすることにその本質的な目的と意義があるのです。
関連記事:【ストレスチェック】義務化と概要│目的やメリットを解説
ストレスチェック調査票において「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者は「高ストレス者」となります。「疲れがずっと抜けない」「休日でも仕事のことが気になって落ち着かない」など、メンタルヘルス不調を示すサインを多く持つ人が該当します。
ただし、それほど極端な自覚症状がなくても、担当業務の責任が重い、業務量が過度に多いなどストレス要因の多い仕事を抱えている人や、上司や同僚からのサポートが乏しい人も、今後メンタルヘルス不調に陥ることが懸念される対象として高ストレス者に分類される場合もあります。
こうしたストレスチェックの結果を活用し、メンタルヘルスセミナーに積極的に参加してほしい従業員・組織をフォローしたり、職場環境を改善する取り組みにつなげることが重要になります。
関連記事:ストレスチェックで高ストレス者が。対応と根本的な改善策とは?
メンタルヘルス不調者の増加防止・未然予防の対策例
企業は、従業員のセルフケアを各自に任せるのではなく、実施しやすいように環境の整備や健康施策を積極的に実施する必要があります。
従業員にセルフケアが必要な背景として、メンタルヘルス不調者が増加している状況が示唆されます。メンタルヘルス不調者の増加防止・未然予防としてセルフケア対策以外に企業が実施できる方法をご紹介していきます。
健康課題の特定
効果的なメンタルヘルス対策を実施するためには、まずはどこに問題があるのかを特定することから始めます。ストレスチェックや従業員サーベイなどを活用すると、解決すべき課題を客観的に見つけることが可能です。
そのために下記のような方法を検討しましょう。
- ストレスチェックの実施
- 従業員サーベイの実施
- 健康診断の実施
これらの方法を実施することで、メンタルヘルス不調者の増加する理由を解明する一助となるだけでなく、メンタルヘルス以外の職場の改善策を検討することにつながります。
定期的な健康施策の実施
従業員に健康的な生活習慣を送ることの重要性を伝えるため、健康施策を定期的に開催することが有効です。上記で抽出した健康課題をもとに具体的に何をすれば良いかを理解し実施することで、業務への効果が表れやすくなります。
関連記事:健康施策の種類一覧|課題解決へと導く健康経営の実践と事例
職場環境の改善
従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、企業の生産性低下にもつながりかねません。上記の点で改善を図り、従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると労働安全衛生法では定められているのです。
職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備なども、職場環境に含まれています。
- 人間関係:コミュニケーションなど
- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど
- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間
とてもシンプルなことですが、働く環境が整うことで、従業員一人ひとりがパフォーマンスを最大限発揮できるようになります。
関連記事:職場環境とは|改善するアイデアと具体例、取り組み事例
健康経営の推進
ここまで見てきたようなメンタルヘルス対策に加え、より効果的に対策を実施するために近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。
健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。
参照:経済産業省「健康経営」
あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。
健康経営として健康プログラムの推進やメンタルヘルス対策を練ることで、事故や傷病予防だけでなく、ストレスの要因への対処や適切なワークライフバランスの達成が可能になります。
関連記事:【徹底解説】健康経営の取り組み方│企業にもたらす効果や事例
福利厚生の充実
働きやすい職場であるかどうかを判断する材料として、福利厚生が挙げられます。特に休暇制度の充実は、従業員のワークライフバランスを確保する観点において重要です。年次休暇や育児休暇、介護休暇、生理休暇、代休などの制度が整っており、またそれらが必要な時に取得しやすい環境であれば、メンタルヘルス対策としても有効でしょう。
これらは、個人でできるセルフケアの強化にもつながります。
関連記事:福利厚生の種類一覧|法定福利厚生から法定外福利厚生まで解説
セルフケア以外のメンタルヘルス対策の実施
セルフケア以外のメンタルヘルス対策として、ストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みで、一次予防・二次予防・三次予防別に実施できる対策があります。
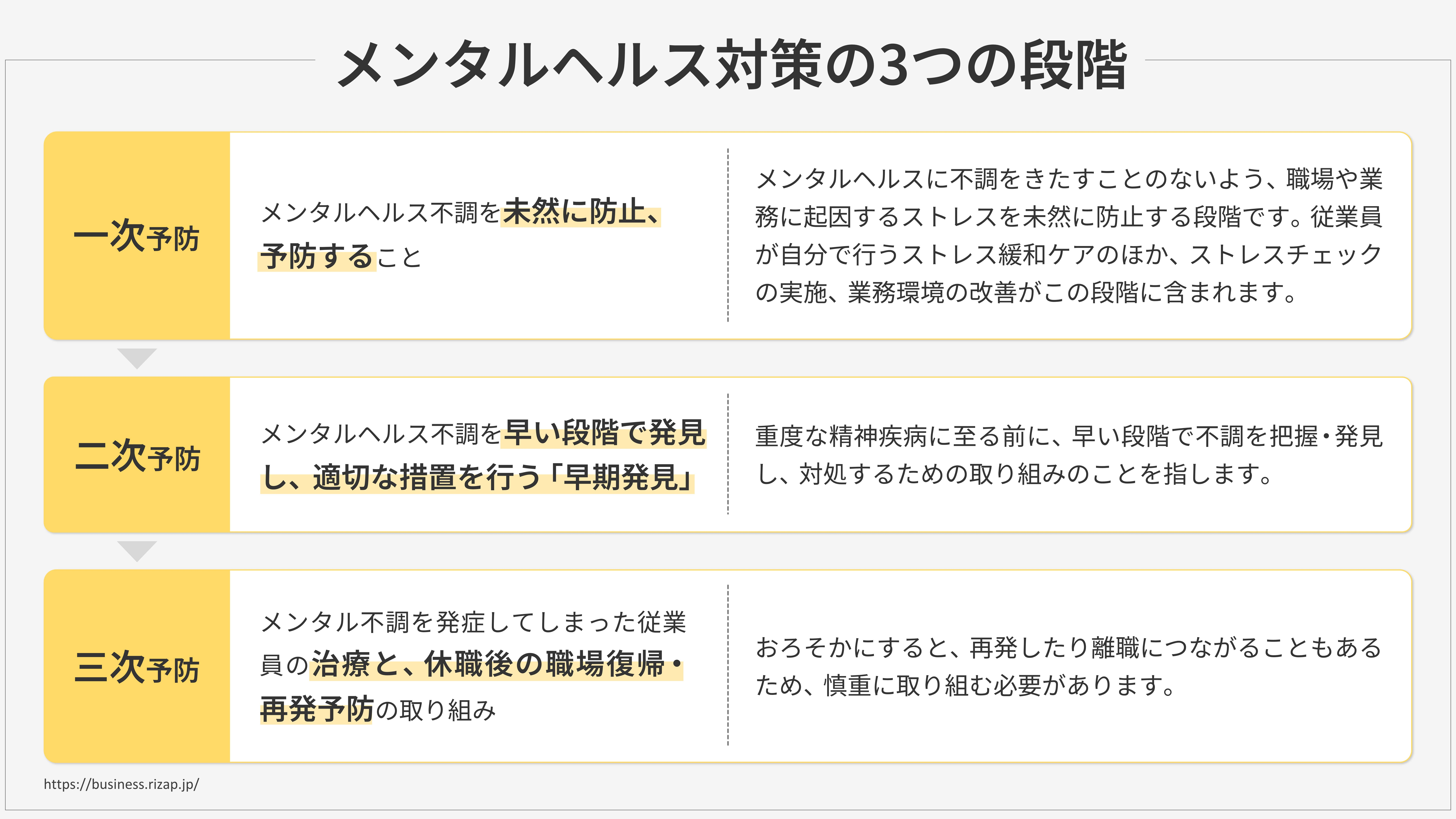
一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。
二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。
三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。
一次予防対策例:メンタルヘルス不調の未然防止につながる取り組み
従業員がメンタルヘルスケアを必要とする状況になる前に、企業としてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが大切です。メンタルヘルス不調の予防につながる取り組みを紹介します。
- メンタルヘルス対策の計画・目標設定をする
- 心理的安全性を高める
二次予防対策体例:早期に発見し、早期治療につなげる取り組み
SOSを上げたり、気兼ねなく相談できる風土醸成により、二次予防が効果的に働きます。ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防に用いられるものですが、副次的な効果としてメンタルヘルス不調の早期発見(二次予防)にもなります。
不調に気付いた時に、ためらわずに相談できる相談窓口を社内外に設置したり、産業医との面談機会を設けることも重要です。
- 健康診断の100%実施を推進する(受診勧奨)
- ラインケアを強化する
- 高ストレス者への面談を実施する
- 若年層も含めた特定保健指導を実施する
- 相談窓口を設置する
三次予防対策例:従業員の復帰支援の取り組み
三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。
まとめ
厚生労働省が掲げる4つのメンタルヘルスケアのひとつが「セルフケア」です。従業員自身が実施するものですが、企業としてもさまざまな施策を整備することで支援することが求められます。
ぜひこの機会に、自社に合ったセルフケア施策の導入を検討してください。
お役立ち資料「セルフケア 対策ガイド」を無料公開
もし、一人ひとりが高い水準でセルフケアを実践できれば、メンタルヘルスの状態は良好に保つことができ、組織の活力や生産性に大きく寄与していくのではないでしょうか。
セルフケアの施策を実施しようとお考えのご担当者様に向けて「セルフケア対策ガイド」をお届けします。
セルフケアに関する情報を体系的におさえ、組織としてセルフケアを高めていくために本資料を作成しました。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
資料をダウンロードする
![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)