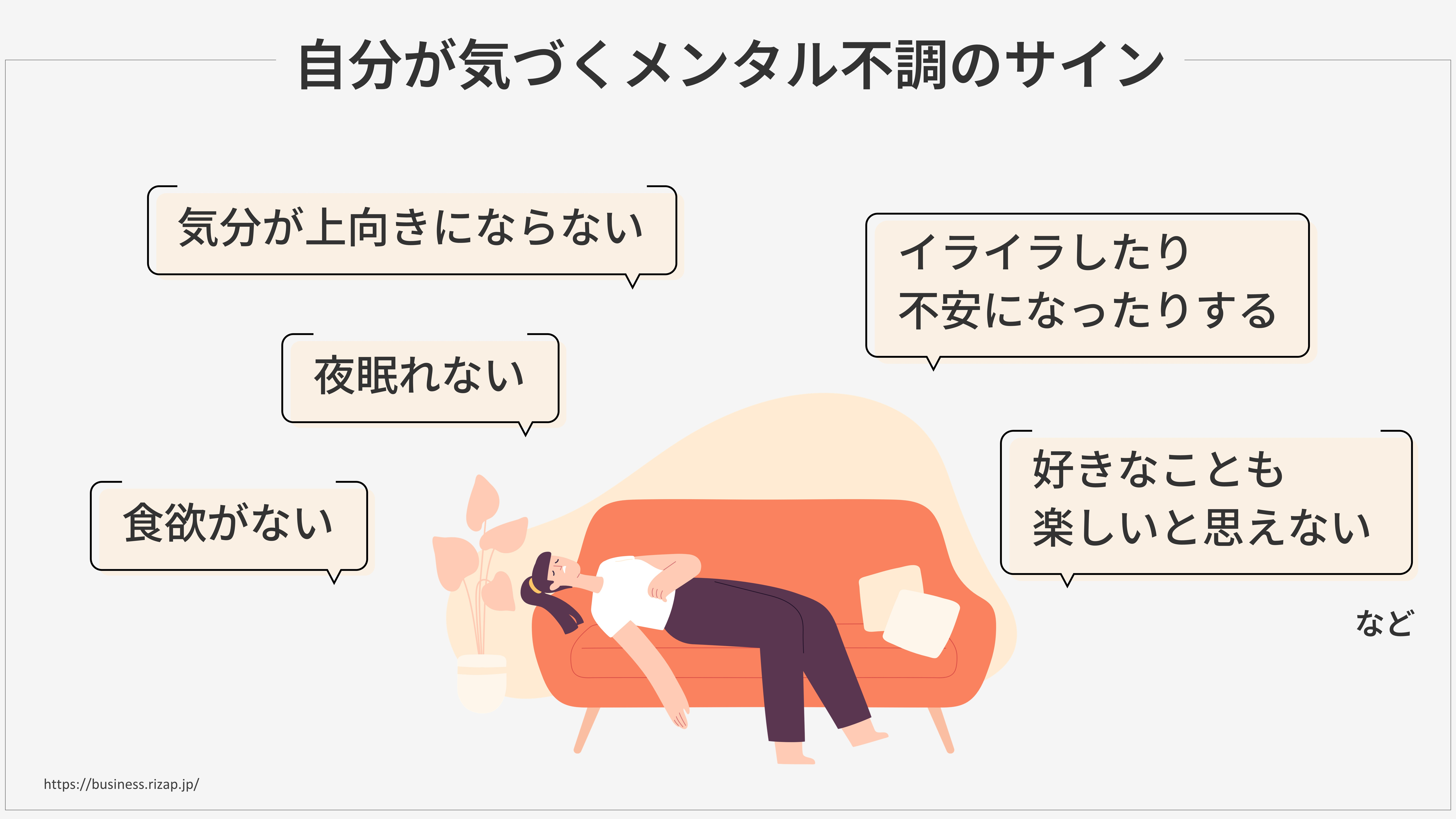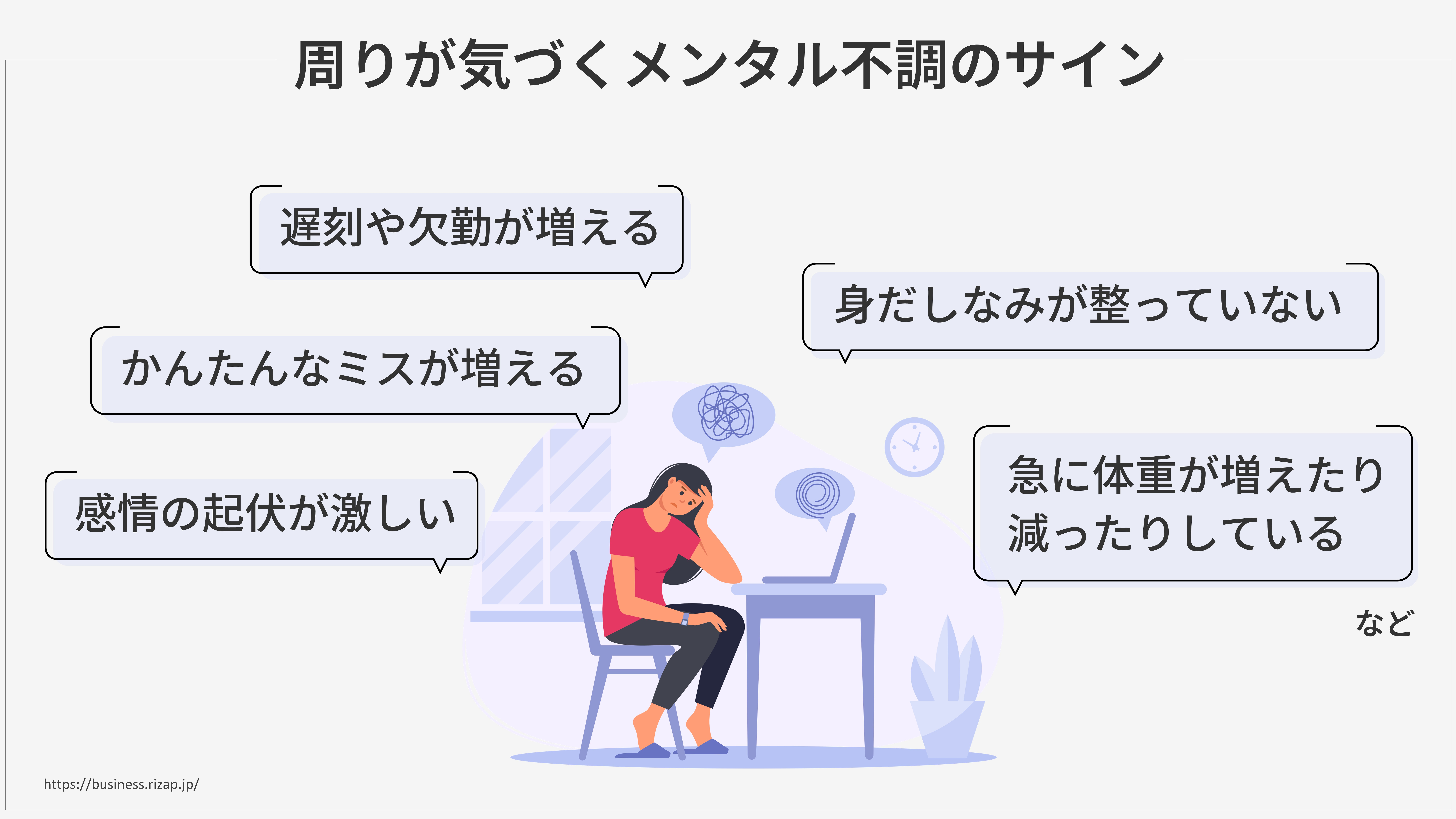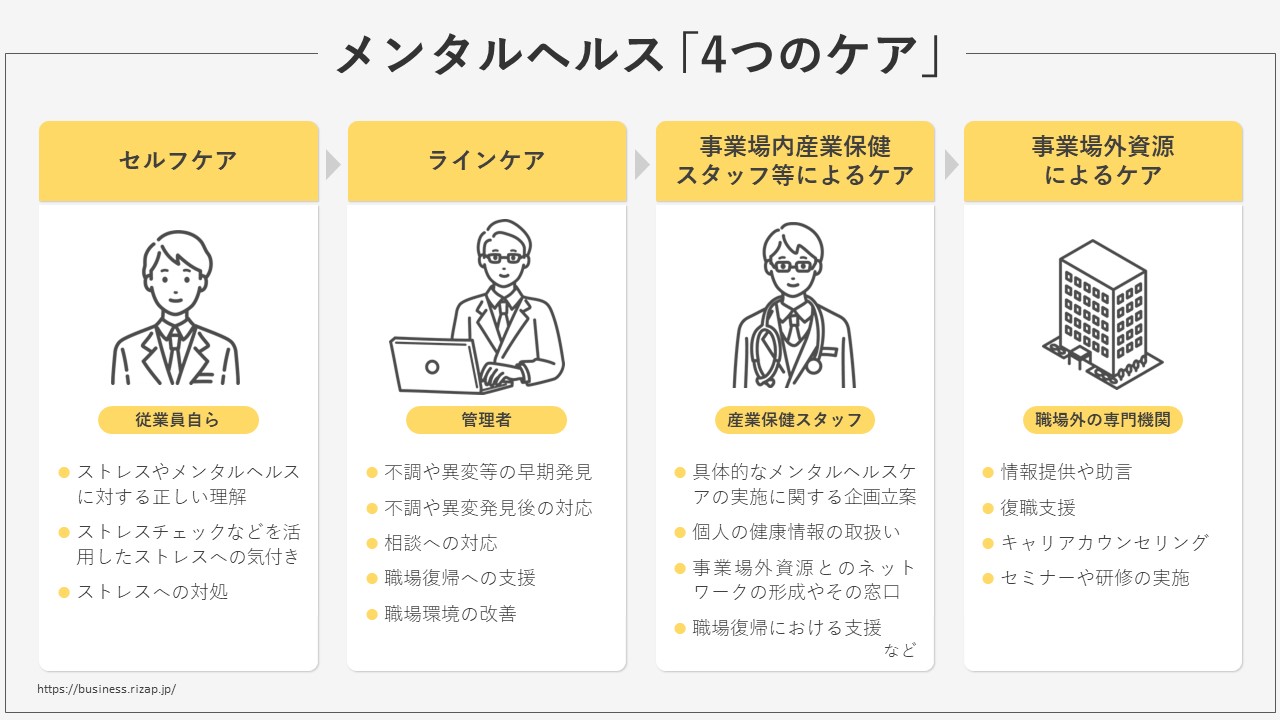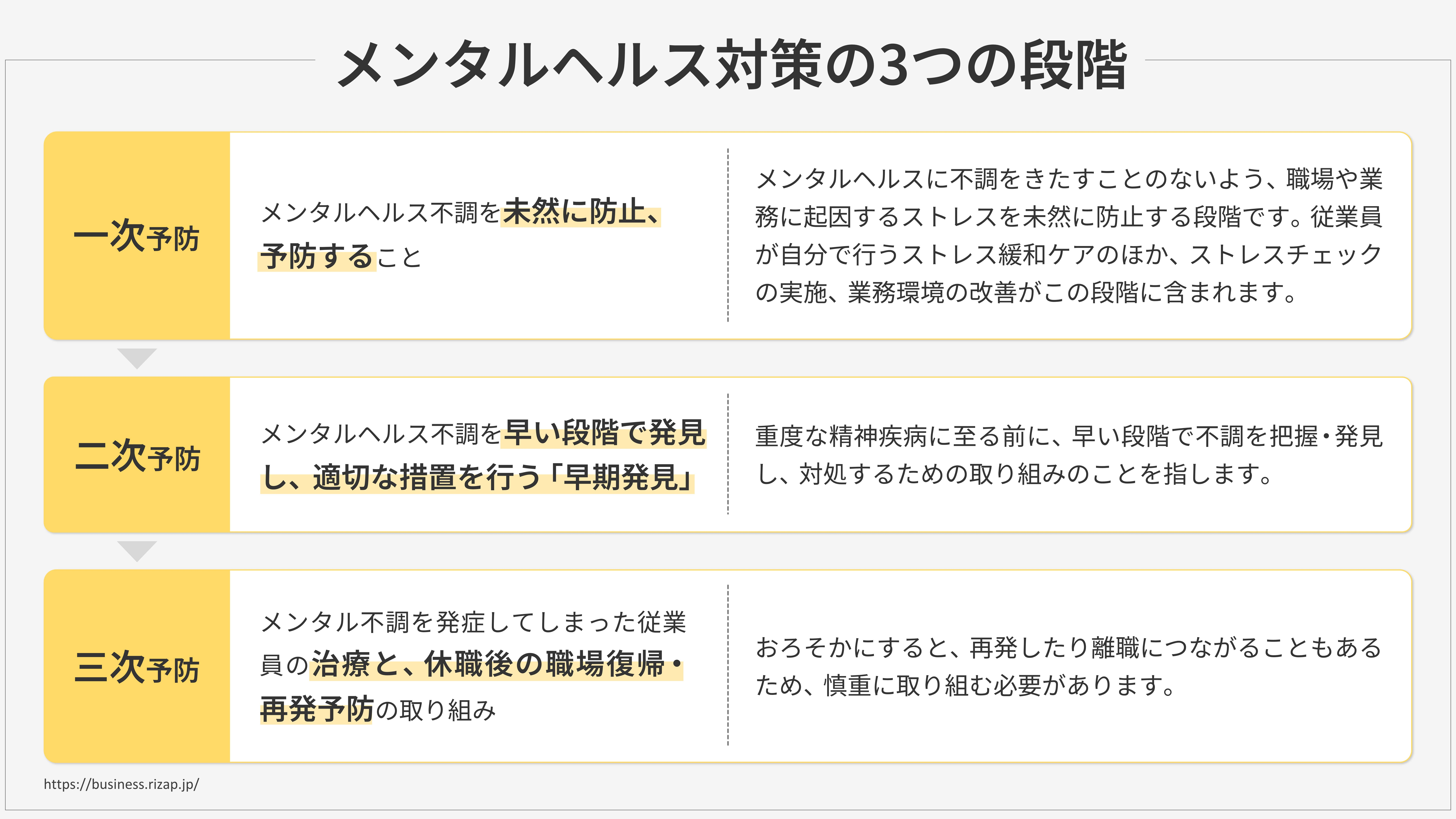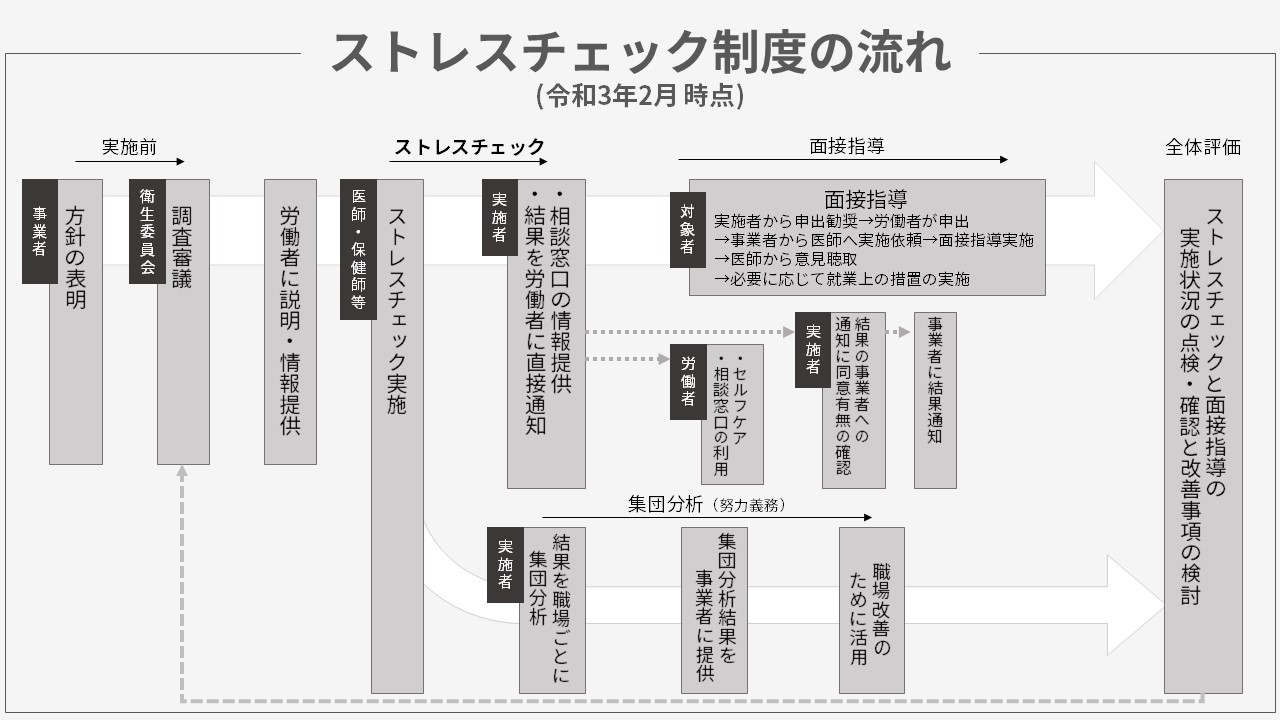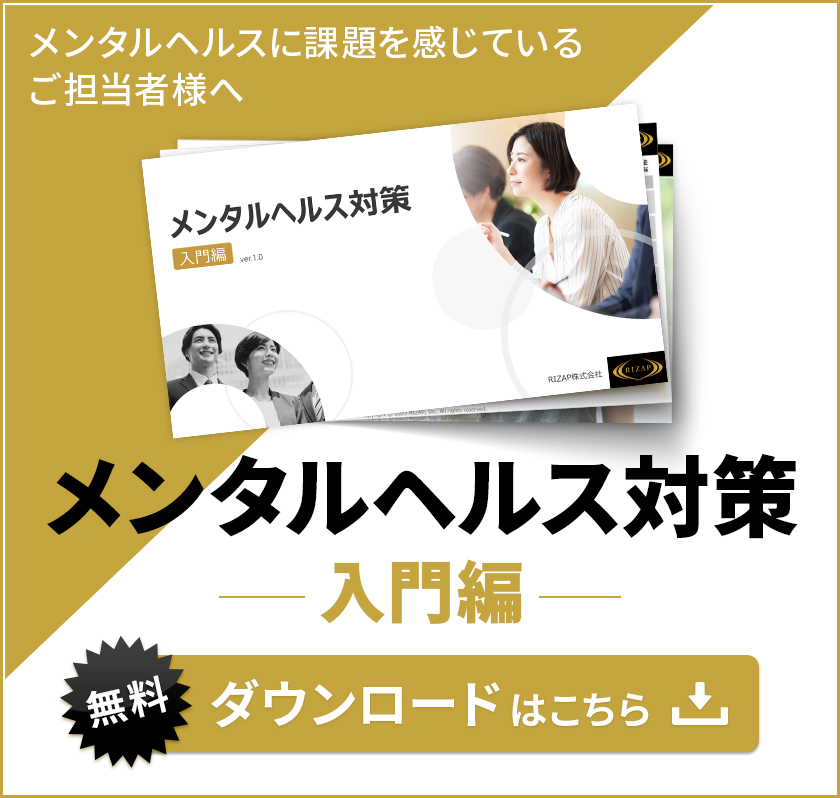誰でも起こりうるメンタル不調とは
健康は、何も身体だけの問題ではありません。
メンタル、つまりこころの健康のことを「メンタルヘルス」と呼び、昨今さまざまなシーンでよく耳にするようになっています。身体と異なり、メンタルの不調は周囲から気づかれにくく、本人もなかなか伝えにくいのが特徴です。その分、悪化しやすいのがやっかいです。
やる気が起きない、気分が沈む、といった状態は普段の生活でもよく見られますが、ストレス負荷の高い状態が続くと、生活面や仕事面で支障が起きます。企業の健康経営が重要視されている昨今、メンタル不調を抱えた従業員が増えれば、休職者や退職者が増加し、事業運営が滞ってしまいかねません。
従業員自身はもとより、雇用している企業にとっても、メンタルヘルスの状態は定期的に把握し、適切に対応していかなければならない重要な課題です。
メンタルヘルス不調の定義
また日本においては厚生労働省が、「メンタルヘルスの不調」※1についてこのように定義しています。
精神および行動の障害に分類される精神障害や自殺のみならず、ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むものをいう。
引用:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
メンタルヘルス不調というと、うつや、パニック障害、適応障害、依存症など、日常生活が困難になるような重度な精神疾患をイメージしがちです。しかし、厚生労働省の定義※1 によると、特別な精神疾患だけを指すものではないことが分かります。
ストレスや強い悩み、不安など、労働者の心身の健康、社会生活および生活の質に影響を与える可能性のある精神的および行動上の問題を幅広く含むもの
引用:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
これはすなわち、疾患ほど重度ではなくても悩みや不安を抱えた状態も指すため、私たちの日常生活でも「メンタルヘルスの不調」は起こりえます。メンタルヘルス不調は特別な人がなるものではなく、誰でもなりうる不調といえるでしょう。
しかし、メンタルヘルス不調になっても多くの場合は治療により回復し、社会の中で安定した生活をおくることができるようになります。最近では、効果が高く副作用の少ない治療薬も出ていますので、以前よりも回復しやすくなっています。
メンタルヘルス不調が起こった場合、体の病気と同じように治療を受けることが何よりも大切です。ただし、早く治そうと焦って無理をすると、回復が遅れることがあります。「焦らず、じっくりと治す」という気持ちで臨むことが回復への近道です。
メンタルヘルス不調のサイン
メンタルヘルスの変化は気づきにくいものであるものの、不調の状態にあると、さまざまなサインが表れます。
ここでは自分自身が気づくものと、周囲の人が気づくものに分けて解説します。
自分が気づくメンタル不調のサイン
働いていれば、仕事でミスをすることも、うまくいかないこともあります。気分が沈むこともあるでしょう。ただ、メンタルが良好なときは、ミスしたことでも前向きにとらえ、「またがんばろう」と思い、再度チャレンジする気力もわいてきます。
一方、メンタルが不調になると、以下のような状態が継続するようになるのが特徴です。
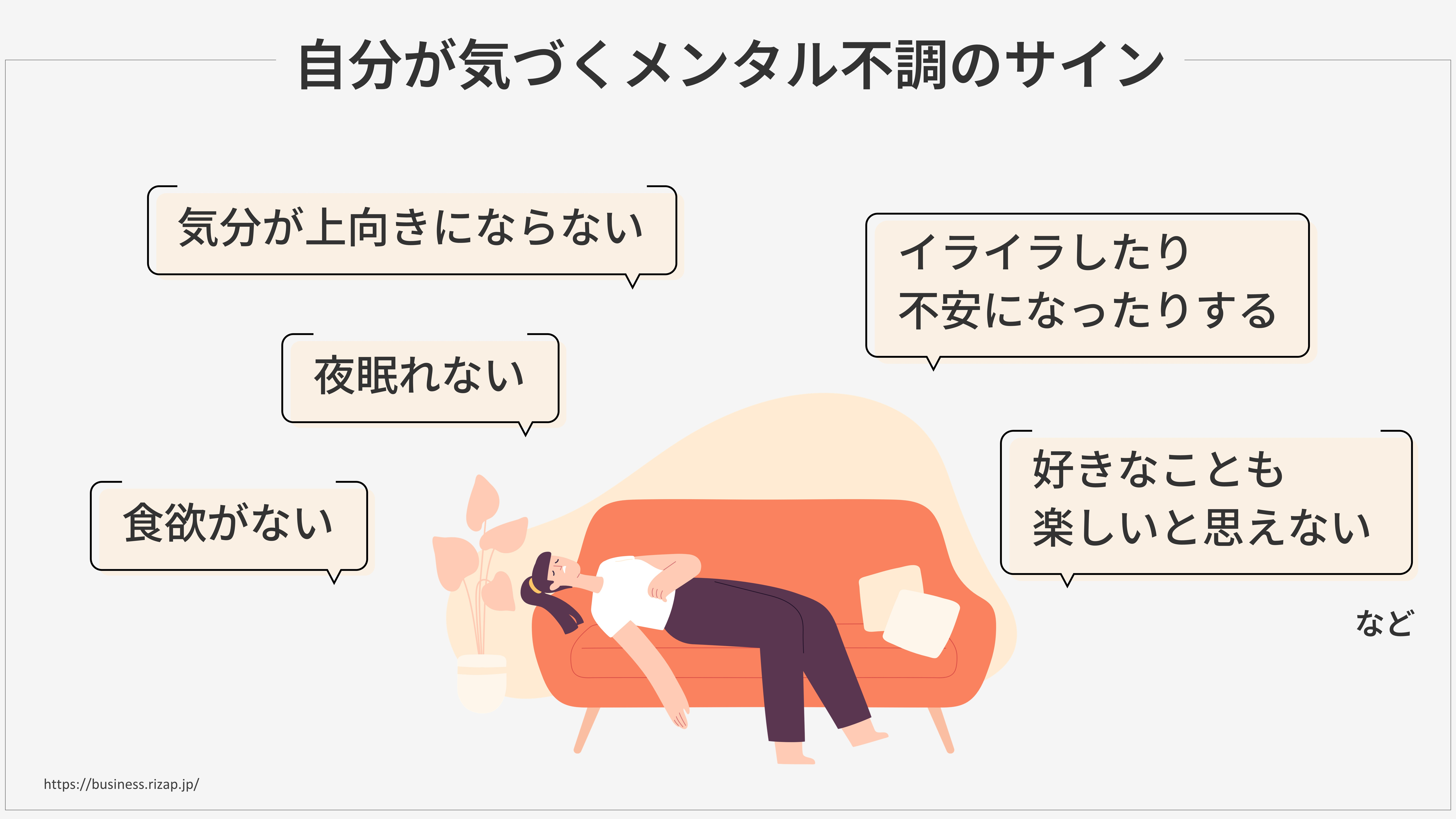
- 気分が上向きにならない
- 夜眠れない
- 食欲がない
- イライラしたり不安になったりする
- 好きなことも楽しいと思えない、など
精神的な不調が身体的な状態へ悪影響を与えることもあります。そのため、メンタル不調の兆候を逃さないように、身体面と精神面の観点から自身の健康状態に気を配る必要があります。
周りが気づくメンタル不調のサイン
本人が不調を自覚しても、なかなか周囲に言い出せないこともよくあります。周りの人が気づきやすい状態としては、以下のようなものが挙げられます。
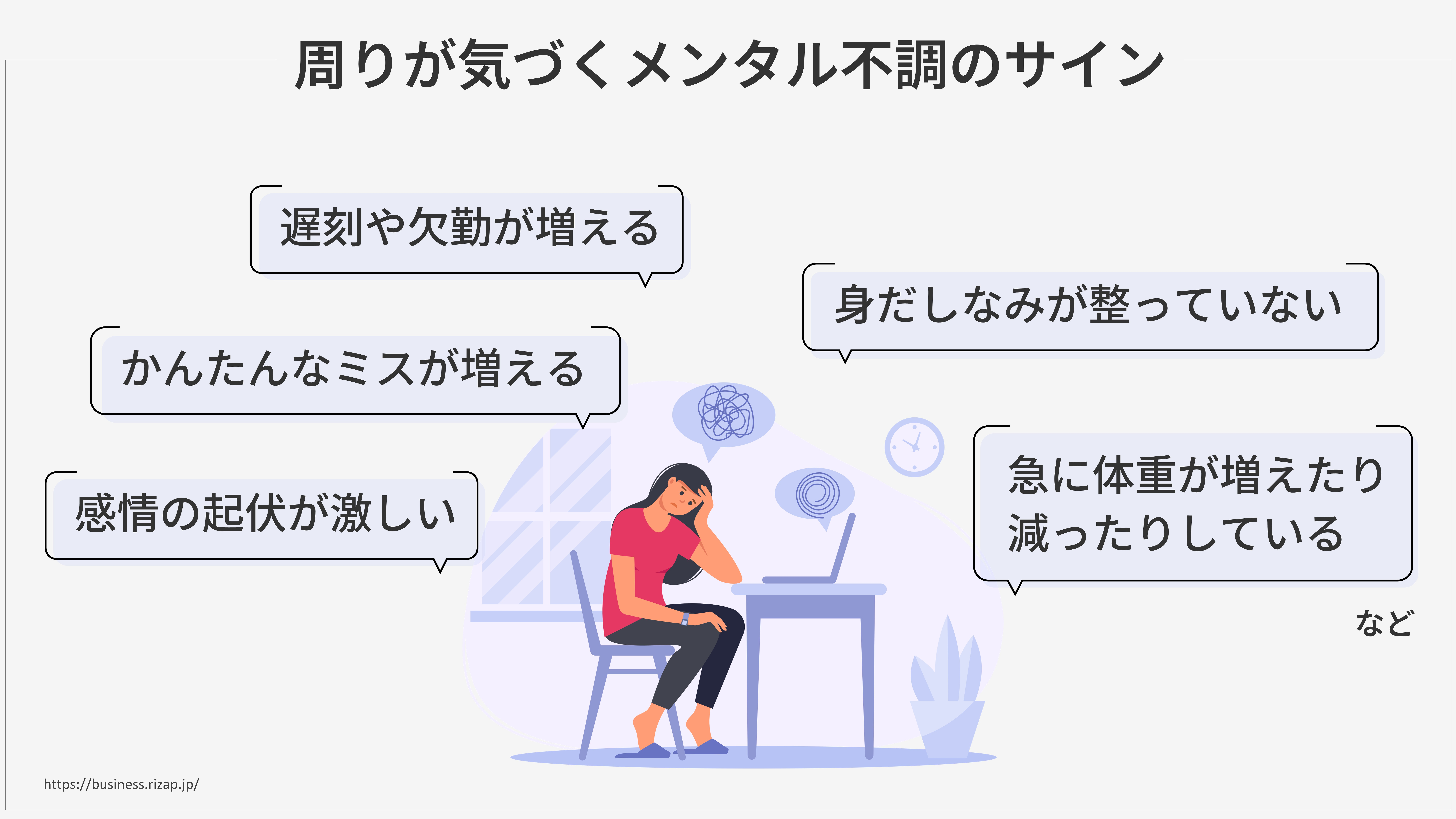
- 遅刻や欠勤が増える
- 身だしなみが整っていない
- かんたんなミスが増える
- 急に体重が増えたり減ったりしている
- 感情の起伏が激しい
以前はとくに問題を感じられなかったのにもかかわらず、急にこうした状態が見られるようになった人がいたならば、もしかするとメンタル不調を抱えているかも知れません。「どうしてこんなこともできないの」といきなり注意したり、怒ったりすると状況が悪化してしまうおそれもあるため、慎重な対応が必要です。
関連記事:職場のメンタルヘルスとは?意味や症状、不調の予防対策
お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をご覧いただけます
近年労働者の受けるストレスは拡大する傾向にあり、メンタル不調は重点的な対策が必要とされています。不調を訴える人の数が増えれば部署、事業部、企業全体の生産性の低下を招き、業績不振にも繋がっていきます。自社のメンタルヘルスに課題を感じ対策を模索されているご担当者様も多いのではないでしょうか?
そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。
どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
資料をダウンロードする
メンタル不調を引き起こしやすい環境・状況
メンタルヘルスが不調になる原因は、人によって異なります。
ここではよくある例を3つ取り上げます。
キャパシティを超えた業務量
日本は少子化の影響もあり、人手不足に悩む企業が少なくありません。業務を遂行するのに必要な人員を集められなければ、従業員一人ひとりの業務負担は当然増えます。就業時間内に終えられない場合は残業することになり、長時間労働につながりがちです。
このように、労働時間や業務量がキャパシティを超えると、焦りや不安、失望などが重なり、心身の健康バランスを崩してしまうことになりかねません。
人間関係の問題
職場では上司やほかの従業員とともに、協力しながら業務を進めていく必要があります。
仕事をスムーズに進めようとすれば、よい人間関係を築いていくことは不可欠といっても過言ではありません。しかし現実は、うまくいかないこともあります。ときには、パワハラやセクハラといったハラスメントが見られたり、ささいなことで人間関係が悪化したりすることもあるかも知れません。
そうした職場に身を置いていると、自分でも気がつかない間に、メンタル不調の症状が現れやすくなります。
異動・昇進など環境の変化
多くの企業では、数年に1度などのスパンで人事異動や昇進をするタイミングがあります。とくに昇進は、本来なら喜ぶべきことですが、本人にとってはストレスになっていることもあります。
いずれも、これまで慣れてきた仕事の環境から離れ、新しい環境に身を置くことになるのが共通点です。「うまくできるだろうか」「早く慣れないといけない」といったプレッシャーや焦り、不安は誰でも持つ感情ではあるものの、より強く感じてしまうと、メンタル不調へとつながってしまいます。
職場でのメンタルヘルスケアの基本的考え方
職場でのメンタルヘルスケアの必要性は年々高まっており、企業において事業者が従業員の心の健康と保持増進のための措置(メンタルヘルスケア)が有効に実施されるよう労働者の心の健康の保持増進のための指針があります。
事業者はメンタルヘルスケアを積極的に推進することを表明するとともに、その実施方法などに関する規程を策定、実施する必要があります。そして実施に当たっては「一次予防」「二次予防」「三次予防」を円滑を行い、「4つのケア」を効果的に推進するために、教育研修・情報提供を行う必要があります。
基本となる4つのケア
メンタル不調と向き合うための有効策として、厚生労働省から「労働者の心の健康の保持推進のための指針」(改正)(平成27年11月)が発表されています。それがメンタル不調と向き合う4つのケアです。
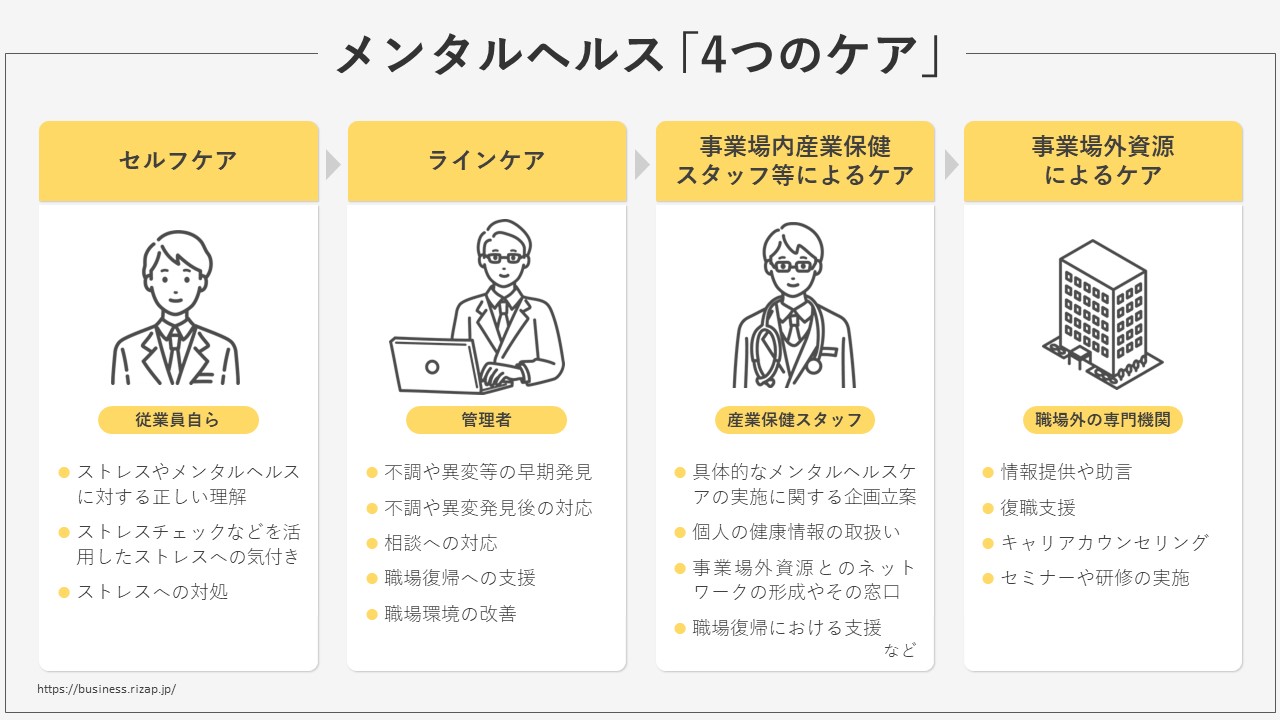
引用:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。事業者は従業員に対して、次に示すセルフケアが行えるように教育研修、情報提供を行うなどの支援をすることが重要です。
ラインケアとは、組織の管理監督者による部下のストレスケアのことです。管理監督者が従業員の具体的なストレス要因を把握し、相談に乗ったり、必要に応じて環境を改善したり、配置転換等の策を講じることを指します。
事業場内産業保健スタッフ等によるケアとは、産業医や衛生管理者、保健師、心理職、精神科医など社内の産業保健スタッフ等による支援のことです。
事業場外資源によるケアとは、メンタルヘルスケアの専門知識を有する外部の機関やサービスを活用することです。
職場のメンタル不調に関する予防・改善対策
メンタルヘルス対策における3つの段階とは、ストレスに対してどの段階で予防・対処するのかという考えに基づいた枠組みで、一次予防・二次予防・三次予防に分かれています。
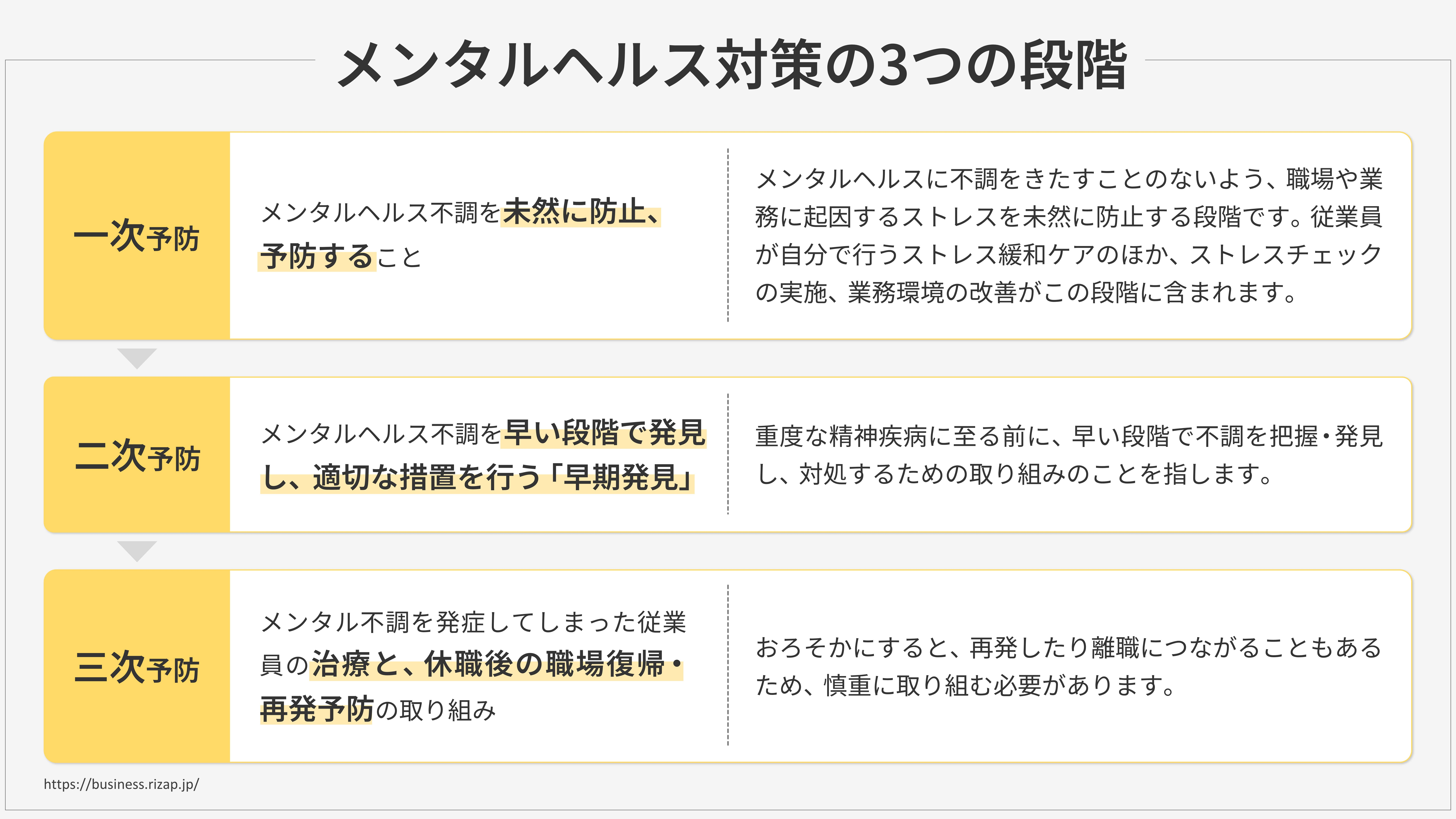
引用:厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」
一次予防とはメンタルヘルス不調を未然に防止、予防することです。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。従業員が自分で行うストレス緩和ケアのほか、ストレスチェックの実施、業務環境の改善がこの段階に含まれます。
二次予防は、メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」です。重度な精神疾病に至る前に、早い段階で不調を把握・発見し、対処するための取り組みのことを指します。
三次予防は、メンタル不調を発症してしまった従業員の治療と、休職後の職場復帰・再発予防の取り組みです。おろそかにすると、再発したり離職につながることもあるため、慎重に取り組む必要があります。
関連記事:メンタルヘルス不調の予防策は? セルフケアや企業が講じるべき対策
メンタル不調を早期発見する方法
メンタルヘルス不調を早い段階で発見し、適切な措置を行う「早期発見」は、重度な精神疾病に至る前に早い段階で不調を把握・発見することで、従業員の健康を守る上でとても重要なメンタルヘルス対策です。
SOSを上げたり、気兼ねなく相談できる風土醸成により、二次予防が効果的に働きます。ストレスチェックはメンタルヘルス対策の一次予防に用いられるものですが、副次的な効果としてメンタルヘルス不調の早期発見(二次予防)にもなります。
不調に気付いた時に、ためらわずに相談できる相談窓口を社内外に設置したり、産業医との面談機会を設けることも重要です。下記に具体的な早期発見方法をお伝えします。
ラインケアを強化する
ラインケアとは、職場のライン上にいる直属の上司が、部下の異常に気付き対応することです。最もベーシックな職場の健康管理方法かもしれません。
部下からの相談に適切に対応したり体調不良等にはやめに気づくには、メンタル疾病に対する偏見を持っていては適切に対応できないことがあります。適切なラインケアの実施は、企業のメンタルヘルス状況を改善・強化させます。管理監督者は日常的に部下と接点があるため、早期発見や問題があった場合のケアにおいて非常に重要な役割を果たします。
働き方の多様化により、異変に気付ける頻度が下がるケースもあるようです。そのため、積極的に1対1の面談機会を作ったり、なるべくコミュニケーション機会を多く設けるなど、工夫や試行錯誤することが必要です。対面でのコミュニケーション機会が減ってきている中で、いかに早期発見するか、また未然にプレゼンティーイズム・アブセンティーイズムを食い止めるかは組織の重要課題の一つとなります。
関連記事:プレゼンティーイズムとは?測定方法と改善対策の具体例
産業医面談に至る前に人事や課・部単位でキャッチアップできていれば、プレゼンティーイズムやアブセンティーイズムに陥る従業員を未然に食い止めることや、適切な人材配置等の措置が可能となります。
課や部の上長または他のメンバーが異変を早めにキャッチアップすることが、組織にとっても従業員にとっても、よりよい「働く環境」になります。
関連記事:ラインケアとは?職場のメンタルヘルス対策、管理職の役割
健康診断を100%の従業員に実施する
企業や組織は、従業員に健康診断を受診させなくてはなりません。
従業員の健康課題を探るためでなく、従業員の健康に対する取り組みの中で健康診断受診率を100%にするということはそれだけで従業員の健康への取り組みの一つとなります。労働安全衛生法第44条では、企業や組織はそこで働く従業員に健康診断を実施しなくてはならないと定められています。
企業や組織は健全な運営を行う必要があり、健康診断はその健全な運営を支える従業員の健康を守るための根幹となります。
全従業員に実施できることで、すべての従業員の健康上必要な再治療や再検査などの受診勧奨をすることに繋がり、様々な疾病の早期発見につながり、対策へと動くことができます。
高ストレス者の面談を推進する
ストレスチェックで高ストレスだった従業員に対しては、これ以上ストレスがかかる状況について放置しないためにも面談や面談に申し出ない場合であっても対応が必要となります。
メンタル不調に陥る状況が回避できるよう、個別の対応を想定しながら放置せずに対応する必要があります。
面談は本人の申し出が必要なため、高ストレス者を強制的に高ストレス者面談に促すことはできませんが、事前の周知や告知の仕方、面談への懸念事項などを払拭することで少しでも多くの高ストレス者を面談実施へ促すことは可能です。
またどうしても面談ができない場合も決して放置せず、高ストレス者や高ストレスにはまだなっていない従業員に対してもメンタルヘルスを未然に防ぐための一次予防対策を辞ししていきましょう。
関連記事:ストレスチェックにおける高ストレス者の判定基準、対応、面談
若年層も含めた特定保健指導を実施する
特定保健指導は、主にメタボリックシンドロームの予防・改善を目的として、40歳以上の従業員に実施される保健指導です。健康増進のためには、問題が発生する前に予防することが理想ですが、そのために有効なのが特定保健指導です。
参考:厚生労働省「特定健診・特定保健指導について」
義務化されているのは基本的に40歳以上ですが、40歳未満の若年層にも実施することで問題の早期発見やヘルスリテラシーの向上が可能になり、より効果的な予防が実現できるでしょう。
関連記事:特定健診・特定保健指導とは?流れや指導内容、実施率向上の解説
相談窓口を設置する
従業員がメンタルヘルス不調について気軽に相談できる窓口を設置することは重要なメンタルヘルスの早期発見対策です。
2020年6月に施行された改正労働施策総合推進法によって設置が義務化されています。中小企業については2022年3月31日までは努力義務となっていますが、2022年4月1日には、大企業と同様に義務化が適用されるため、全ての企業において体制整備が必要となってきます。こうした観点からも、相談窓口を設置し、社内に周知して従業員の利用を促すことはリスクヘッジにもつながります。
社内に設置する方法と、社外に設置する方法の2つがあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。
社内の場合は体制を作り、メールや電話、面談等の相談方法を決めることで設置できるという手軽さがあります。
しかし社内に不信感や疑念を抱いている従業員は相談しづらい側面もあるため、社外に相談窓口を設置することも有効です。必要に応じて検討すると良いでしょう。
関連記事:EAPとは?導入されている理由、効果、気を付けるポイント
メンタル不調に気づいた際の対応
チームのスタッフや部下がメンタルヘルス不調かな、と気づいた際には放置せず、対応について検討していく必要があります。どういった対応が求められるのか、ポイントを紹介します。
相談しやすい環境をつくる
日常的に相談しやすい環境であり、「困ったことがあったら話そう」、「伝えたら適切なアドバイスや対応をしてもらえる」という、信頼に基づいた関係性であることが不可欠な前提条件となります。
一朝一夕に理想的な上下関係やチーム内の状態が築けるものではありませんが、常日頃のやり取りや行いからそういった環境ができていきます。心がけていきましょう。
傾聴する
チーム内の中でも特に管理監督者は、日常的に、部下からの自発的な相談に対応する役割を担っています。そのためには、部下の話をじっくりと聴くことがとても重要です。
日頃からこのような話の聴き方ができれば、チーム内の関係は良い状態で維持されやすくなります。
傾聴のポイント
1.相手を受け止める
相手に対して関心を持ち、関心を持っていることを表情や態度で相手に伝える。
2.相手の立場に立つ
もしも自分が相手と同じような立場に置かれていたら、相手と同じようなことを言ったり、したりするんだろうなぁと考えながら、話を聞く。
そうすることが話の聞き方が批判的になることを防ぎ、相手に話を聴いてもらっているという気持ちを持たせる。
引用:厚生労働省「こころの耳 15分でわかるラインによるケア」p.8
本人の状態によっては産業医や専門医等への相談を勧めることも有効です。
しかし中には、人に悩みを相談することに抵抗がある方や、大仰にしたくない、周囲から変な見られになるんじゃないか、などといった考えや不安から、本人が産業医等に相談することに心理的な抵抗を示す場合もあります。
そういった場合は、「産業医に話せ」「医者に行け」と強制したり、聞いた悩みを拒否するようなことはせず、「あなたの代わりに私が相談に行ってくるよ」と本人に伝え、合意を得た上で、相談を受けた従業員が管理者や産業医や人事、専門家等の第三者に相談し、その内容をフィードバックするなどの対応をしてみましょう。
自己流にならないよう対応に注意する
日々、良い関係でチームを構築するために3つのNG例を挙げます
比較や押し付け言動に注意
管理監督者の場合「私が20代の頃は」「営業たるもの」など自身の経験や価値観と比較したり、押し付ける言動はNGです。同様にして、「最近の若い子は」「うちの会社は」などの大きな主語を使う点にも注意が必要です。
なぜなら、その価値観や括りに共感しない(できない)人が一定数いるからです。
押し付けられた、大きな括りに入れられた、という感情は反発を買い、共感されることなく次第に信頼を失っていきます。
適当な取りつくろいに注意
うわべを取りつくろっただけの言動は本人に着実に伝わります。
「適当に話を合わせただけ」「ちゃんと見てくれていない」「ちゃんと聞かずに頷いているだけ」という想いが募っていくと、信頼を失い、部下のモチベーションを下げることとなります。精神誠意、本人と向き合うことが本質です。
「ついうっかり」やる気を削ぐ一言に注意
「この仕事向いてないんじゃないか」、「もっと頑張ってよ」などの言葉は要注意です。励ます意図で口にした場合でも、些細な一言がモチベーションを下げたり、反感を買うことがあります。
気にかかる一言を言われた側は、長期にわたって忘れることができず、場合によってはトラウマに発展するようなこともあります。そういった「気付かない内の、ついうっかり」の言動で本人を追い込むことがあることを認識しましょう。
個人情報、人権へ配慮する
相談を受けた場合に重要なのは個人情報や人権への配慮です。健康情報や個人情報の保護、また人権の保護や本人の意思尊重に努めなければなりません。これは人道的な観点からだけでなく、法令としても遵守する必要があります。
人事に相談したり、第三者に相談するなど、情報の収集・管理・使用に際しては、なんらかの方法で本人の同意を得ることが原則とされています。
このように、関連する法令や、社内規則を遵守し、コミュニケーションのなかで得た本人の情報を正当な理由なく他に漏らさないようにしましょう。
人事部門や産業医を巻き込んで対応する
相談を受けた場合に、親身になって考え、何とかしてあげたいという想いや責任感の強さから、管理監督者が過剰なストレスを抱え込み、メンタル不調に陥ってしまうというケースがあります。
一人で抱え込まず、適切に産業医や外部機関、人事部門に相談をすることが重要です。
メンタルの不調を改善するための個人の対策
メンタル不調は、いつ、誰にでも起こりうることです。もし普段の自分と比べて少し違和感を持ったり、明確に症状を感じたりしたときには、改善に向けて対策を取ることが大切です。
ここでは、本人ができる改善策について、3つ紹介します。
十分な休息、休養を取る
メンタル不調が表れる原因のひとつに、日々の疲れの蓄積があります。そのため、仕事の合間にリフレッシュしたり、夜は睡眠時間をできるだけ確保したりするなど、脳と身体を休めることが大切です。仕事で行き詰まることがあっても、いったん離れて休んでみると、新しいアイデアや解決策がひらめくかも知れません。
趣味などレクレーションの時間をとる
メンタル不調を改善するためには、メリハリを付けて生活することも大切です。就業時間は集中して仕事に取り組まなければなりませんが、それ以外では、自分の好きなことや趣味、レクリエーションにあてる時間を持つのもおすすめです。自分なりにストレス発散できる機会を持てれば、また心機一転、仕事に取り組めるようになります。
ストレッチなどリラックスできる状況をつくる
同じ姿勢で仕事を続けていると、肩こりや腰痛に悩まされることも増えがちです。また、長時間同じ姿勢が続くと、横隔膜や肋骨を適切に使用した呼吸が出来なくなってしまい、自律神経の乱れを引き起こす可能性があります。自律神経の乱れは精神的な不調の原因となりかねません。デスクワークが一段落すれば、立ち上がって、軽く歩いたり、ストレッチをしたりすることで、身体のこりがほぐれてすっきりします。
食生活、栄養状態を改善する
メンタルは、食事からも影響を受けます。栄養状態を適正に保ち、健やかな食生活を維持することも、メンタルヘルスにおいて重要です。
極端な例ですが、空腹や飢餓状態が続くことで情緒不安定になるケースもあります。また、特定の栄養素の欠如が関係していることもあります。そのため、バランス良くさまざまな栄養素を日常的に摂取することが重要です。
メンタルヘルスやストレスと関係する栄養素としては、以下のようなものが挙げられます。
- ビタミンB群
- ビタミンC
- ビタミンD
- マグネシウム
- 鉄
- 亜鉛
- カルシウム
関連記事:【食事セミナー一覧】健康増進・食生活改善の企業向け取り組み例
ストレスチェックで職場のメンタル状況を把握する
ストレスチェックは、メンタルヘルス不調を未然に防ぐために、自分のストレスがどのような状態なのかを可視化する検査でメンタルヘルスの一次予防として非常に重要です。
これによって高ストレス者はストレスを溜めすぎないように注意したり、専門の医師に相談したり、業務の軽減を事業場に行ってもらったりするなどの対応を行えるだけでなく、部署ごとのストレス状況把握と改善対策が可能であり、それによって職場環境の改善方法を発見することにつながります。
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、従業員のストレス状態を調べるための簡易的な検査のことです。ストレスチェックは基本的にセルフチェック方式で行われ、従業員は選択式の調査票を通して、自身のストレス状態を回答していきます。
ストレスチェックを実施することで高ストレス者本人に自覚を促せるだけでなく、部署ごとのストレス状況把握と改善対策が可能であり、それによって職場環境の改善方法を発見することにつながります。
ストレスチェックは「労働安全衛生法」が改正されて、常時50人以上の従業員がいる事業所において、2015 年12月から毎年1回、この検査を全ての従業員に対して実施することが義務付けられました。なお、従業員が50人未満の事業所に関しては、実施義務も報告義務もありません。当分のあいだは努力義務に留まるとされています。
参照:厚生労働省「ストレスチェック制度導入マニュアル」
しかしメンタルヘルスの一次予防の役割として重要であることから、50人未満の事業所であっても実施することが推奨されています。
事業者側のメリットとしては、ストレスチェックを実施することで従業員のメンタルヘルス不調を未然に防いだり、早期対応をしたりできることが挙げられます。
高ストレス者の多い職場は人間関係もギスギスしやすく、不注意などによるヒューマンエラーも起きやすくなります。高ストレス者を放置せずメンタルケアに取り組めるきっかけとなると共に、ストレスチェックの分析を行うことで職場に内在するストレス要因を見つけることが可能です。大きな問題となる前に対策を打つことで、職場環境の改善や労働生産性の向上を期待できます。
実施の流れ
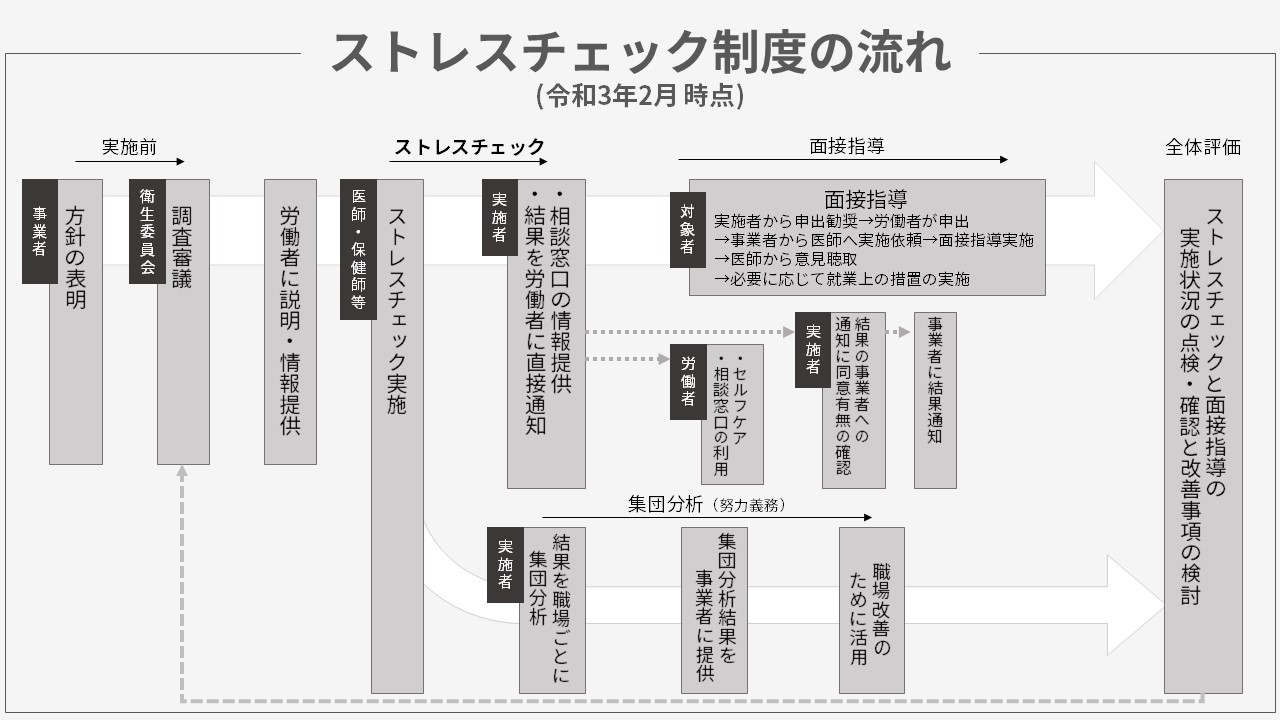
ストレスチェックには様々な事前準備が必要となります。事前準備においては、事業所の衛生委員会で以下に挙げる事柄を議論し、実施方法の検討をすることが必要です。ここで話し合った結論は社内ルールとして明文化し、全ての従業員に周知します。
- 【対象者の決定】ストレスチェックは誰に実施させるのか
- 【時期と頻度の決定】ストレスチェックはいつ実施するのか
- 【質問票の決定】どんな質問票を使ってストレスチェックを実施するのか
- 【高ストレス者の選び方】どんな基準でストレスの高い人を選ぶのか
- 面接指導の申し出は誰にすればいいのか
- 面接指導はどの医師に依頼して実施するのか
- 集団分析はどんな方法で行うのか
- ストレスチェックの結果は誰が、どこに保存するのか
実施の際には質問票作成と配布を行い、次にそれらを集計して評価、通知を行います。ITシステムを利用して、オンラインで実施することもできます。
使用する質問票は、①ストレスの原因に関する質問項目②ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目③労働者に対する周囲のサポートに関する質問項目が含まれていれば、特に指定はありませんが、何を使えばよいか分からない場合は、厚生労働省が推奨する「職業性ストレス簡易検査表(57項目)」を使用することができます。
ストレスチェック結果の評価方法、基準は実施者の提案・助言、衛生委員会における調査審議を経て、事業者によって決定します。
活用方法
回収した質問票をもとに、医師などの実施者がストレスの程度を評価し、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。高ストレスとは、自覚症状が高い方や自覚症状が一定程度あり、ストレスの原因や周囲のサポートの状況が著しく悪い方をさします。
結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)は、実施者から直接本人に通知されます。結果は企業には返ってきません。
ストレスチェック結果で「医師による面接指導が必要」とされ た従業員から申出があった場合は、医師に依頼して面接指導を実施します。面談実施後、面接指導を実施した医師から就業上の措置の必要性の有無とその内容について意見を聴き、それを踏まえて労働時間の短縮など必要な措置を実施します。
そして一次予防を主な目的とするストレスチェック制度の趣旨を踏まえ、ストレスチェックの結果を踏まえて従業員本人のセルフケアを進めるとともに職場環境の改善に取り組むことができます。ストレスチェックの実施者に、ストレスチェック結果を一定規模の集団(部、課、グループなど)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらうことで集団ごとのストレス状況を把握します。
集団分析及び職場環境の改善は法的には努力義務にすぎませんが、職場に潜在するストレス要因を特定し、それらを組織的に改善していくことで、ストレス負荷の低い職場環境の構築が可能です。
関連記事:ストレスチェック制度とは?対象者、目的、メリット、実施方法
メンタル不調を予防する企業の対策
メンタルヘルス不調を未然に防止、予防することを一次予防といいます。メンタルヘルスに不調をきたすことのないよう、職場や業務に起因するストレスを未然に防止する段階です。
従業員がメンタルヘルスケアを必要とする状況になる前に、企業としてメンタルヘルス不調を未然に防ぐことが大切です。メンタルヘルス不調の予防につながる取り組みを紹介します。
解決すべき課題を特定・目標設定・実施計画を練る
効果的なメンタルヘルス対策を実施するためには、まずはどこに問題があるのかを特定することから始めます。ストレスチェックや従業員サーベイなどを活用すると、解決すべき課題を客観的に見つけることが可能です。課題を特定したら終わりではなく、課題を踏まえて目標設定・実施計画まで行い対策を実施しましょう。
課題を特定する
課題を特定する方法としては、ストレスチェックや従業員サーベイ等が考えられます。
メンタル不調のリスクは若手が多いと思われがちですが、その考えは誤りです。心の病を抱えているのは10~20代と、30代、40代はほぼ同じ割合になるため、幅広い層を対象に実施することが望ましいです。そのため、健康診断の結果分析だけでなく、全従業員を対象としたアンケートを実施し、その結果を活用し現状把握を正しく行う必要があります。
健康計画・目標設定をする
メンタルヘルス対策は、中長期的視点に立って、継続的かつ計画的に行われるようにすることが重要でその推進に当たっては、事業者が従業員の意見を聞きつつ事業場の実態に則した取り組みを行うことが必要です。
事業場内産業保健スタッフ等が一次予防~三次予防まで気を配り、中心的な役割をしながら実施していくために、衛生委員会等において十分調査審議を行い、「心の健康づくり計画」を策定することが必要です。
セルフケアを強化する
従業員のメンタルヘルスを考える中で最も重要なのがセルフケアです。「セルフケア」は、従業員が自分自身で行うメンタルヘルス対策を指します。
セルフケアは従業員一人ひとりが自らのストレスを予防し、気付いた時に適切に対処することです。簡単そうですが実は正しい知識がないと適切に対処できません。
例えば、体や気持ちに異変が生じていても「今の自分は、うつ病かもしれない」と、自発的に気付いて対応できる従業員ばかりではありません。また異変の度合いや、生じる症状や頻度は、人によってそれぞれであるため、判断が難しい場合があります。
このセルフケアが十分にできれば、不調を未然に防いだり、重度に至る前に対処でき、組織全体でストレスへの対応力が強化されることとなります。また不調を感じた場合も重症化することなく改善できれば、企業にとってのダメージも軽減できます。
ストレスの認知や、その反応に自ら気付くためには、従業員一人ひとりがストレス要因に対する反応や、心の健康について理解するとともに、気付こうとする姿勢が必要です。自ら気付き、対応する「セルフケア」を適切にできるようになるには、教育研修の機会を設けて、意識を高めていくことが重要です。
関連記事:企業で実践するセルフケアとは?個人・職場での取り組み例
健康リテラシーを高める
全ての健康問題に影響すると考えられている健康リテラシーを高めることは、メンタルヘルス対策にも有効です。健康リテラシーを高めることで「健康意識を高めること」につながるのです。
メンタルヘルス対策を実施する際にも健康リテラシーの高い従業員に対して施策を実施することで効果が最大限に高まります。
健康リテラシーとは、「自分に必要な健康情報を入手し活用する能力のこと」です。健康リテラシーが高いと正しい情報を理解でき、自身の健康状態に応じて活用することができます。
例えば、健康診断などで疾病の早期発見や、重症化する前に軽症の段階で治療できることもあるでしょう。あるいは健康な方の場合は、維持増進のために、積極的な取り組みを行うなどの工夫ができます。
健康リテラシーを身につけ、セルフケアを従業員自身がすすめられることで健康状態が改善されアブセンティーイズムやプレゼンティーイズムの改善につながり、結果的には労働生産性の向上にもつながります。
高い健康リテラシーを身に着け、適切な行動ができる従業員が増えることで、社内全体の健康レベルは底上げされます。
関連記事:従業員の健康リテラシー向上策を知ろう
運動習慣を定着させる
運動することでセロトニンの分泌が増加し、興奮やイライラを鎮めることで心の安定につながります。また、睡眠の質を向上させるメラトニンも分泌されるため、運動の継続はメンタルヘルス対策に効果をもたらすことが期待されるのです。
また運動で体を動かすことは、精神的ストレスの発散にもつながります。「疾病予防および健康に対する身体活動・運動の効用と実効性に影響する要因」で記載されている身体的な効果は2つあります。
- ストレスの解消、うつ病の予防・改善に有効
- シェイプアップし、自己イメージが改善
運動によってストレス発散やセルフイメージ・自信の向上ができると、仕事面においても、集中力や目標達成能力の向上といった良い影響を及ぼします。また、従業員同士で運動不足解消に取り組むことは、従業員同士のメンタルヘルス維持やコミュニケーション促進にも効果的です。
関連記事:運動とメンタルヘルスの関係とは?有効性と従業員への取組み
運動機会の促進にあたり、研修会内での運動イベントの実施など単発の施策に加えて、運動習慣の定着に向けた継続的な施策も同時に行うことが重要となります。
▼実施施策例
- ウォーキングイベントへの実施
- 運動会などのスポーツイベントの実施
- ラジオ体操の実施
- 運動サークルの運営
- 徒歩や自転車での通勤環境の整備
- スポーツクラブへの補助金
- 福利厚生の整備
- 運動セミナーの実施
RIZAP運動セミナー資料(無料)のダウンロードはこちら
食生活の改善を後押しする
適切な量とバランスの良い食事は運動習慣と並んで従業員の心身を活性化し、業務のパフォーマンスをあげる取り組みとして欠かせません。職場において、従業員が自ら正しい食事を選べるように、継続的な情報提供や実践活動、サポートが必要になります。
▼実施施策例
- 社食などで健康づくり支援メニューを提供・栄養素やカロリー等の表示
- 健康に配慮した食事・飲料の提供や補助
- 外部事業者等の栄養指導・相談窓口の設置
- 食生活改善アプリ提供等のサポートの実施
- 特定保健指導の実施
- 食事セミナーの実施
関連記事:健康経営を左右する食生活改善の取り組み、企業事例
休養を見直す
長時間労働は過労死やメンタルヘルス不調につながる可能性があります。そのため企業はリスクマネジメントの視点からも、長時間労働によって従業員の健康が損なわれないように、時間外労働の削減や、有給休暇の取得促進、福利厚生の充実等を行うことが求められています。
▼実施施策例
- 有給休暇取得目標の設定
- ノー残業デーの導入
- 残業を事前承認制にする
- 勤務間インターバル制度を導入する
- 業務繁閑に応じた営業時間を設定する
- 健康増進となる福利厚生を導入する
RIZAP福利厚生・法人会員資料(無料)のダウンロードはこちら
職場環境を改善する
従業員が1日の多くの時間を過ごす職場環境が悪いと従業員に大きな負担がかかり、企業の生産性低下にもつながりかねません。上記の点で改善を図り、従業員が働きやすい快適な職場環境を形成する配慮義務が事業主にあると労働安全衛生法では定められています。
職場環境とは、単に作業をする場所そのものに限られません。作業方法や疲労回復するための設備なども、職場環境に含まれています。
- 人間関係:コミュニケーションなど
- 業務環境:空調照明など~設備レイアウトなど
- 業務内容:裁量権、負荷の量、労働時間
ストレスチェックの結果によって、これらの職場環境の必要性と改善のための対策が浮き彫りになります。ストレスチェックを形骸化することなくメンタルヘルス対策の一次予防として生かすことで働く環境が整い、従業員一人ひとりがパフォーマンスを最大限発揮できるようになります。
関連記事:職場環境とは|改善するアイデアと具体例、取り組み事例
健康経営を推進する
ここまで見てきたようなメンタルヘルス対策に加え、より効果的に対策を実施するために、近年重視されている「健康経営」の視点を取り入れることも大いに役立ちます。
健康経営とは、『従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する経営手法』です。
参照:経済産業省「健康経営」
あくまで企業が用いる経営手法ですので、従業員の健康を促進することは手段であり、目的は組織の活性化・生産性の向上であり、最終的には業績向上、企業価値の向上を目指します。
職場で健康プログラムを実施することで従業員の行動変容をもたらします。最も効果を発揮するのは各施策の単発での実施ではなくに提供されるのではなく、組織の戦略の中心に位置づけられ継続的に実施されているときです。
健康経営として健康プログラムの推進やメンタルヘルス対策を練ることで、事故や傷病予防だけでなく、ストレスの要因への対処や適切なワークライフバランスの達成が可能になります。
健康経営の取組みとして、「メンタルヘルス不調者への対応」や「特定保健指導の推進」など従業員の健康増進につながる項目が含まれています。そのため、健康経営と併せてメンタルヘルス対策を推進することで、より効率的に従業員の健康を保持・増進ができ、生産性の向上へ取り組み効果を最大化することができます。
健康経営スタートガイド(無料)のダウンロードはこちら
関連記事:【徹底解説】健康経営とは?
まとめ
従業員のメンタル不調を放置していると、事故が発生しやすくなるほか、生産性も落ちるおそれがあります。昨今、企業にとって重要な命題とされている「健康経営」の一環として、メンタルヘルスの知識を身に付け、従業員本人と連携しながら適切に対応していくことが大切です。
お役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」を無料で公開
メンタルヘルス対策をこれからやろうとお考えの方の中には「何から手を付けるのが良いか迷う方」「基礎知識をおさらいしたい方」「どんな施策でどんな効果が得られるか知りたい方」も多いのではないでしょうか?
そこで、メンタルヘルス対策を推進するお役立ち資料「メンタルヘルス対策入門編」をお届けします。
どんな視点でメンタルヘルスを捉えるのが良いのか、自社の課題を把握するためには何が必要なのかなどを、基礎的な情報から、有効な施策や事例などを交えて総合的にご紹介しています。
どなたでも無料でダウンロードいただけますので、ぜひご活用ください。
資料をダウンロードする
![RIZAP [ ライザップ ]法人](/_assets/img/logo.svg)